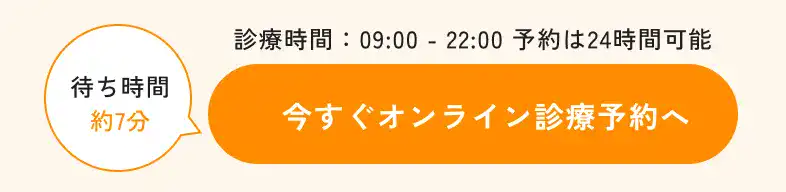「会社を休むのに、診断書を提出するよう言われたけど…どうすればいいんだろう?」
「体調が悪くて病院に行くのもしんどい。そもそも診断書っていくらかかるの?」
突然診断書が必要になると、どこで、どうやって、いくらで発行してもらえるのか、分からないことだらけで戸惑ってしまいますよね。
この記事では、診断書に関するあらゆる疑問にお答えします。
- 断書の基本的な役割と使用目的
- 病院での具体的なもらい方と伝え方のコツ
- 気になる費用や、後から発行してもらえるかという疑問
- オンライン診療での発行相談について
この記事を読めば、あなたが今すぐ何をすべきかが明確になります。
診断書とは?何のために必要なの?
診断書とは、医師が診察に基づいて患者の健康状態(病名、症状、必要な療養期間など)を専門的な視点で証明する「公的な書類」です。
口頭での説明だけでは不十分な場面で、あなたの健康状態を客観的に証明する重要な役割を果たします。
主に、以下のような目的で使用されます。
- 会社関連: 休職・復職の手続き、長時間労働と症状の関連性の証明、欠勤の正当な理由の証明
- 学校関連: 欠席・休学・留年の手続き、試験の追試申請
- 各種手続き: 生命保険の給付金請求、傷病手当金の申請、障害年金や公的な支援制度の利用など
あなたが正当な権利を行使したり、適切な配慮を受けたりするために、診断書は不可欠な書類です。
診断書のもらい方
Step 1. 医療機関を受診する
診断書は医師のみが作成できる書類のため、まずは病院やクリニックを受診し、医師の診察を受けることが絶対条件です。
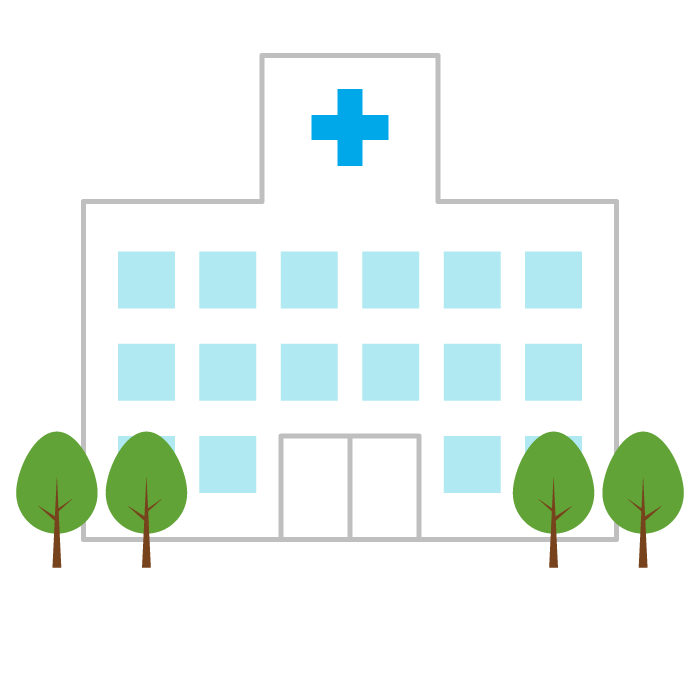
Step 2. 診断書が必要な旨と「使用目的」を伝える
診察の際に、「診断書が必要です」と医師に伝えましょう。
その際、「何のために使うのか(例:会社に休職を申請するため)」を具体的に伝えることが最も重要です。使用目的によって、記載すべき内容や重点が変わってくるためです。

Step 3. 必要な項目を伝える(もしあれば)
提出先から「〇日間以上の休養が必要、という文言を入れてください」「病名だけでなく、症状も詳しく書いてください」といった書式上の指定がある場合は、その内容を正確に医師に伝えましょう。

Step 4. 会計・受け取り
診察が終わったら、受付で会計をします。診断書の発行には、診察料とは別に文書作成料がかかります。
簡単な内容であればその日のうちに受け取れることが多いですが、後日になる場合もあります。
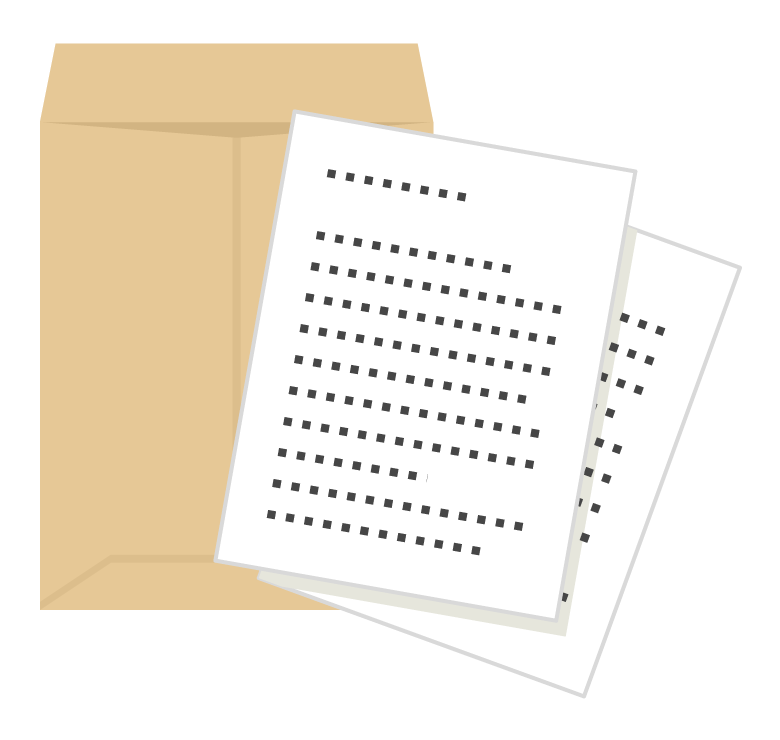
診断書の費用は?保険適用される?
診断書の発行費用に関して、最も重要な点は「公的医療保険が適用されない」ということです。
これは、診断書の発行が病気の治療を目的とした「医療行為」ではないためで、費用は全額自己負担の「自由診療」扱いとなります。
料金は各医療機関が独自に設定できるため金額は様々ですが、一般的な相場は2,000円〜5,000円程度です。ただし、生命保険会社指定の複雑な書式などの場合は、10,000円程度になることもあります。
会計時に慌てないよう、診断書を依頼する際に受付などで料金を確認しておくと安心です。

診断書はあとから書いてもらうことはできるの?
「あの時休んだ日の診断書が、今になって必要になった…」というケースもあるでしょう。
結論から言うと、原則として後からでも発行は可能です。
医師はカルテ(診療録)に基づいて診断書を作成するため、過去に診察した事実があれば、その内容を証明することができます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- カルテの保存期間: 法律で定められたカルテの保存期間は5年です。これを超えると記録が破棄され、発行できなくなる可能性があります。
- 受診していない期間は証明不可: その医療機関で診察を受けていない期間について、さかのぼって証明することはできません。
「〇月〇日の診察について診断書が欲しいのですが…」と、まずは電話などで受診した医療機関に問い合わせてみましょう。
通院が困難なら「オンライン診療」での発行相談も
「そもそも体調が悪くて、病院まで行けない…」
「仕事が忙しくて、平日に病院に行く時間がない」
「精神的な理由で、外出や待ち時間が大きなストレス…」
診断書が必要でも、通院そのものが大きなハードルになることは少なくありません。
そんな時は、ご自宅からスマホ一つで医師の診察を受けられるウチカラクリニックのオンライン診療でご相談いただくことも可能です。
当院では、医師が診察の結果として診断書の発行が妥当・可能と判断した場合、最短即日で発行し、PDF形式で安全にお送りすることが可能です(別途、原本の郵送も承ります)。
オンライン診療での発行の流れ

- オンライン診療を予約
- ビデオ通話で医師の診察を受ける
(症状や診断書の使用目的を詳しくお伝えください) - 医師が発行可能と判断
- 決済後、PDFで診断書を送付
当院での発行の注意点
- 医師の判断が必須:
診察の結果、症状によっては診断書が発行できない場合や、対面での診察をお勧めする場合がございますのでその点はご了承下さい。
- 記載項目の確認:
必要な記載項目など、事前に提出先へご確認いただくとスムーズです。発行後の患者様都合の診断書の修正には新規文書作成料が発生します。
- 証明期間:
証明期間は最大1か月です。当院を受診していない期間の証明は基本的にはできかねます。
- 初診での対応:
原則初診のみでの対応は致しかねます。
インフルエンザなどの急性疾患関連や登校・登園のための証明書などでは例外もありますので、当院公式LINEまでお気軽にご相談ください。

よくある質問Q&A
最後に、診断書に関するよくある質問にお答えします。
Q. 診察したその日にすぐもらえますか?
症状が明確で簡単な内容であれば即日発行可能な場合が多いです。
ただし、詳しい検査が必要な場合や、医療機関が混雑している場合は後日になることもあります。
Q. 診断書を自分で作成したり、偽造したりするとどうなりますか?
絶対にやめてください。診断書は医師のみが作成できる「公文書」に準ずる重要な書類です。自分で作成したり、内容を書き換えたりすると、「有印私文書偽造罪」という犯罪に問われる可能性があります。
また、偽造した診断書を会社などに提出した場合、詐欺罪に問われたり、懲戒解雇の理由になったりするリスクもあり、絶対に許される行為ではありません。

Q. 診断書の費用は、医療費控除の対象になりますか?
いいえ、診断書の発行費用は治療行為ではないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。 た
だし、例外として、高額療養費の申請や傷病手当金の請求など、「治療を受けるために直接必要な書類」と認められるケースでは、控除の対象となる場合があります。詳しくは税務署にご確認ください。
Q. どんな内容が書かれていますか?
一般的には、必要に応じて患者情報(氏名・生年月日)、病名、症状の経過、必要な治療や療養期間、医師の氏名などが記載されます。
Q. 診断書に有効期限はありますか?
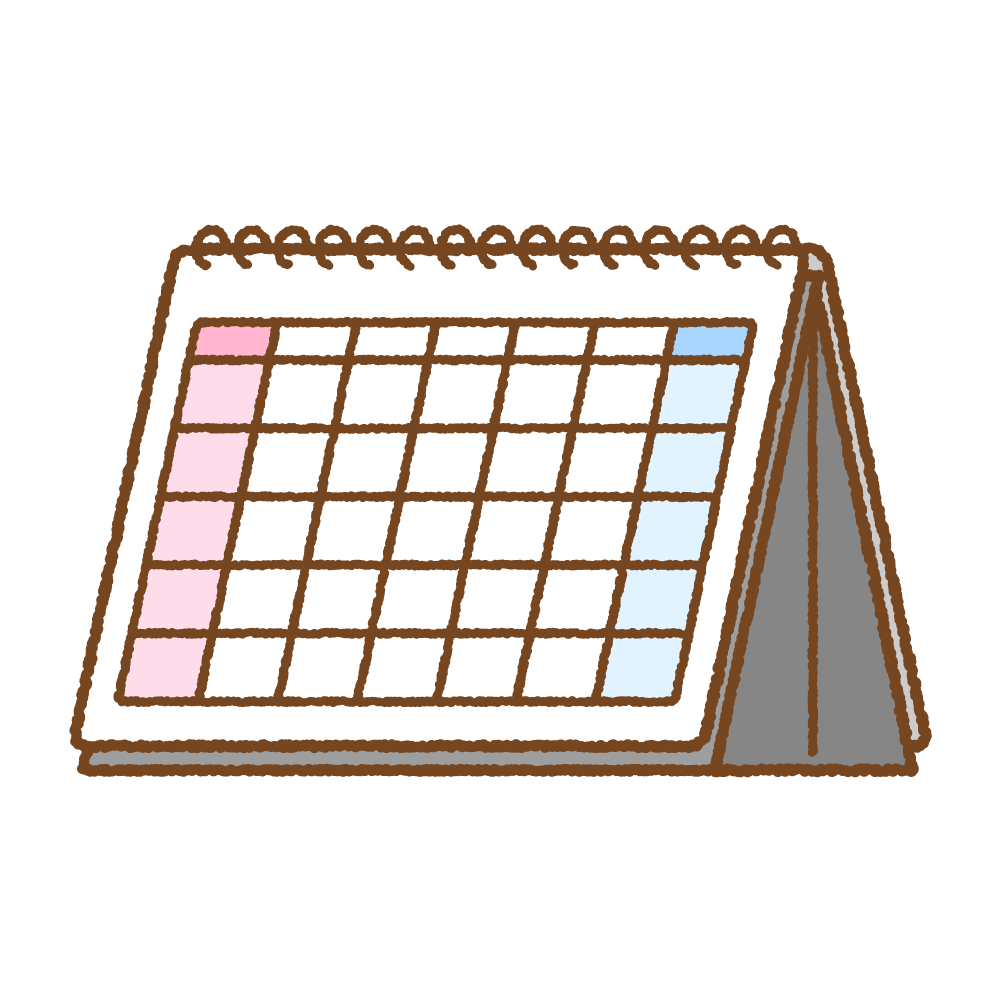
書類自体に法的な有効期限はありませんが、提出先が「発行から3ヶ月以内」などのルールを設けている場合がほとんどです。事前に確認しておきましょう。
Q. 会社を休職するのに、診断書は絶対に必要ですか?
法律で定められているわけではありませんが、ほとんどの会社の就業規則で、一定期間以上(例:1ヶ月以上)休む場合には診断書の提出が義務付けられています。
診断書は、あなたの休職が「病気やケガの治療のため」という正当な理由であることを客観的に証明する役割を果たします。スムーズに休職手続きを進めるためにも、基本的には必要とお考えください。
Q. うつ病や適応障害でも診断書はもらえますか?
はい、もらえます。うつ病や適応障害、不安障害といった精神的な不調も、治療が必要な病気です。医師が診察の結果、「精神的な不調により、業務の遂行が困難で休養が必要な状態」と判断すれば、診断書は発行されます。我慢せずに、まずは専門医にご相談ください。
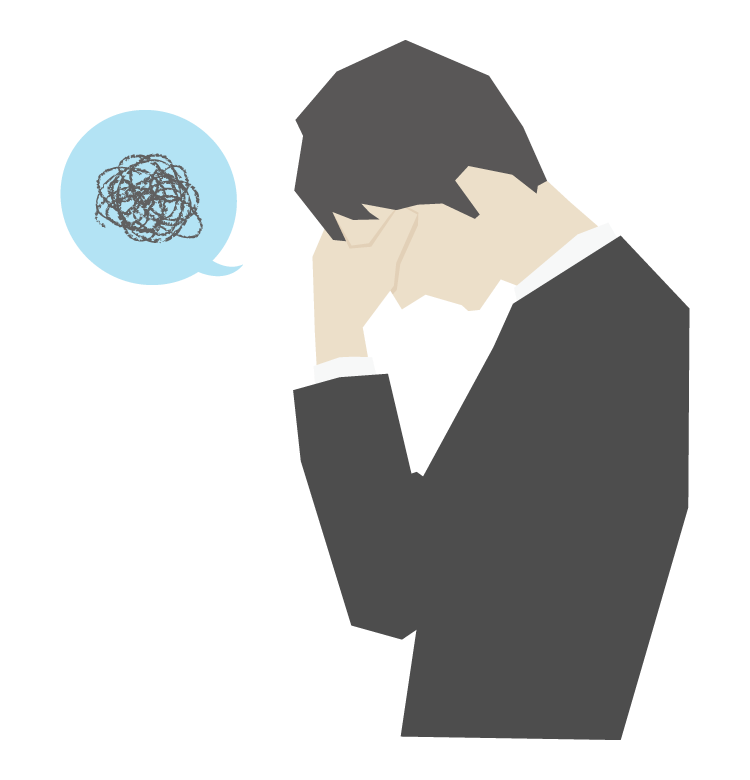
Q. 傷病手当金申請書と診断書は、何が違うのですか?
両方とも休職の際に必要なものなので混同してしまいがちですが、この2つは目的と提出先が全く異なる別の書類です。
- 診断書:主に会社や学校に提出し、病気やケガで休む必要があることを証明するための書類。
- 傷病手当金申請書:休んだ期間の生活保障(手当金)を受けるために、健康保険組合へ提出する専用の申請用紙。
休職手続きで会社に提出するのが『診断書』、その休んだ期間の生活費を健保に請求するのが『傷病手当金申請書』と覚えておくと分かりやすいです。
【こちらの記事もチェック!】
傷病手当金ってなに?休職中もお金がもらえる?支給の条件や申請書について医師が解説!
傷病手当金申請書類の記入は「医療行為」。適切な証明が重要。
ここで一つ、大切なことをお伝えします。
傷病手当金申請書類(医師の意見書)への記入は、医師が診察に基づき「労務不能」であるという医学的な判断を証明する、責任の重い「医療行為」です。
そのため、信頼できるクリニックは、単に患者様のご要望に応えるためだけに、安易に「労務不能」であると証明することはありません。
傷病手当金は、療養中の皆様の生活を支えるための大切な公的制度であり、その申請には客観的な医学的根拠が求められます。
当クリニックでも、オンライン診療で得られる情報が不十分なまま安易に書類へ記入することは、結果的に申請が承認されないなど患者様ご自身の不利益に繋がる可能性や、制度そのものの信頼性を損なうことになるため、記入をお断りする場合がございます。
医師が「対面診療が必要」と判断するのは、患者様の症状を正確に把握し、皆様が正当な保障を受けるために最も安全で確実な証明を行うためです。何卒ご理解いただけますと幸いです。

まとめ
今回は、病院で貰える診断書について解説しました。
- 診断書は、休職や各種手続きで自身の健康状態を証明する公的な書類です。
- もらう際は、医療機関を受診し「何に使うか」という目的を明確に医師に伝えましょう。
- 費用は保険適用外で、2,000円〜5,000円が相場です。
- 通院が難しい場合は、オンライン診療で相談するという便利な選択肢もあります。
診断書は、あなたの権利を守り、安心して療養や手続きを進めるための大切なツールです。
もし通院が難しい、時間がない、すぐにでも相談したいといった状況であれば、ぜひウチカラクリニックのオンライン診療をご活用ください。