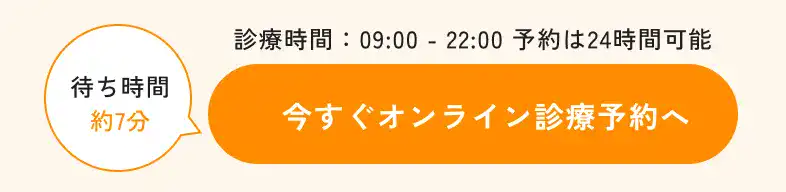「市販薬を試してもスッキリしない…」「お腹が張って苦しい…」 つらい便秘の悩み、一人で抱えていませんか?
病院で処方されるお薬は、あなたの便秘のタイプに合わせて選ばれる、とても心強い味方です。 この記事では、現在お医者さんから処方される便秘薬について、その種類や効果、副作用などを一つひとつ丁寧に解説していきます。飲み薬はもちろん、坐薬や浣腸、漢方薬まで網羅していますので、「今飲んでいる薬はどんなお薬なんだろう?」という疑問もスッキリ解消するはずです。
ご自身の治療への理解を深め、つらい便秘から解放されるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
つらい便秘や下痢は
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
内科のオンライン診療
目次
市販薬と処方薬の違い
病院でお医者さんから処方されるお薬には、市販薬にはない大きなメリットがあります。
処方薬は市販薬には含まれていない専門的な成分を使えたり、同じ成分でもより多く含んでいたりするため、高い効果が期待できます。
また、便秘治療は日々進歩しており、近年では新しい仕組みで作用するお薬が次々と開発されていますが、こうした最新の治療薬は医師の診断がなければ使うことができません。
さらに経済的な面でも、診察代はかかりますが、お薬代には健康保険が適用されるため、結果として自己負担額を抑えられるケースも少なくありません。
このように、
- 効果の高さ
- 治療の選択肢の広さ
- 経済的な観点
から、つらい便秘や慢性的な便秘に悩んでいる場合は、自己判断で市販薬を使い続けるよりも、一度お医者さんに相談して、ご自身の症状に本当に合ったお薬を処方してもらうことが、根本的な解決への近道と言えるでしょう。

処方される便秘薬 【内服薬】
まずは、口から飲むタイプのお薬(内服薬)をご紹介します。
お薬がどうやって便秘を解消するのか、その仕組み(作用)によっていくつかのタイプに分かれています。
整腸剤
直接的に便を出すというよりは、お腹の中の環境を整えるサポーターのようなお薬です。
善玉菌を増やして腸内フローラのバランスを良くすることで、お通じをスムーズにする手助けをします。作用がとても穏やかなため、他の便秘薬と一緒に処方されることもよくあります。
ミヤBM錠/細粒

胃酸に強く、生きたまま腸に届く「酪酸菌」が主成分です。
腸内で善玉菌を増やし、悪玉菌の働きを抑えてくれます。抗生物質と同時に飲んでも影響を受けにくいのが特徴です。
【詳細はこちら】
→ミヤBM
ビオフェルミン錠剤

ヒト由来の乳酸菌を複数配合しており、小腸から大腸まで広く腸内環境を整えてくれます。
古くからあり、多くの人に馴染みのある安心感のあるお薬です。
【詳細はこちら】
→ビオフェルミン
浸透圧性下剤
腸を無理に刺激せず、便に水分を集めることで、カチカチに硬くなった便を柔らかくしてくれるお薬です。
お腹が痛くなりにくく、クセにもなりにくいため、便秘治療の基本として、まず最初に処方されることが多いタイプです。
マグミット錠(酸化マグネシウム)

昔から広く使われているお薬です。医療現場では親しみを込めて「カマ(酸化マグネシウムの“マグ”を逆から読んだもの)」と呼ばれることも。
副作用は少ないですが、腎臓が悪い方は血液中のマグネシウム濃度が高くなりすぎないよう注意です。
【詳細はこちら】
→マグミット
→酸化マグネシウム
モビコール配合内用剤

比較的新しいタイプのお薬で、一番の特徴は小さなお子さん(2歳以上)から大人まで使えること。
水に溶かして飲むので、錠剤が苦手な方でも服用しやすいです。体内の水分バランスに影響を与えにくい設計になっています。
【詳細はこちら】
→モビコール
上皮機能変容薬/胆汁酸トランスポーター(IBAT)阻害薬
「腸の壁から水分を分泌させる」という新しい仕組みで便通を促すお薬です。これまでの薬では効果が不十分だった、つらい慢性便秘症の治療で活躍しています。
アミティーザカプセル(ルビプロストン)

小腸に作用して水分泌を促し、便を柔らかくします。
副作用として吐き気が出ることがあるため、食後に服用します。
【詳細はこちら】
→アミティーザカプセル
リンゼス錠(リナクロチド)

お腹の張りや痛みを伴う「便秘型過敏性腸症候群(IBS-C)」の治療にも使われるお薬です。
腸からの水分泌を促すだけでなく、腸の知覚過敏(痛みを感じやすい状態)を和らげる効果も期待できます。こちらも食前に服用します。
【詳細はこちら】
→リンゼス錠
グーフィス錠(エロビキシバット)

胆汁酸の再吸収を抑えるというユニークな仕組みで、大腸への水分泌と腸の運動をダブルで促進します。
効果の発現が比較的早く、服用から数時間で便意を感じることも。食前に飲むのがポイントです。
【詳細はこちら】
→グーフィス錠
刺激性下剤
にぶくなった大腸の動きを、直接刺激して活発にするパワフルなお薬です。
「今すぐ出したい!」という時に高い効果が期待できますが、毎日使い続けると腸が刺激に慣れてしまうため、症状がひどい時だけ飲む「頓服(とんぷく)」として使われるのが基本です。
ラキソベロン内用液・錠(ピコスルファートナトリウム)

液体タイプが有名で、コップの水に数滴たらして飲みます。1滴単位で量を細かく調整できるため、自分に合った効き目を探しやすいのが大きなメリットです。
効果は飲んでから7~12時間後くらいに現れます。
【詳細はこちら】
→ラキソベロン
→ピコスルファートナトリウム
センノシド(プルゼニド)

古くからある代表的な刺激性下剤で、主成分は生薬の「センナ」です。
薬局で買える市販薬にも同じ成分のものが多くあります。飲んでから8~10時間ほどで効果が現れるため、寝る前に飲むことが多いお薬です。
【詳細はこちら】
→センノシド(プルゼニド)
処方される便秘薬 【外用薬】
飲み薬で効果がない場合や、特に出口付近で便が詰まっている場合、即効性が求められる場合などに外用薬(坐薬・浣腸)が使われます。
坐薬
おしりから直接入れることで、直腸に働きかけるお薬です。
新レシカルボン坐剤
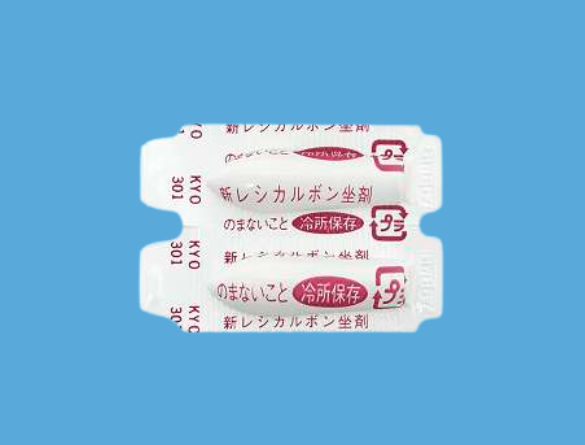
おしりに入れると体温で溶け、中でシュワシュワとした炭酸ガスが発生します。
このガスが腸を優しく広げ、「うんちがしたい!」という自然な便意を呼び起こしてくれます。浣腸と比べて作用が穏やかで、習慣性も少ないのが特徴です。
【詳細はこちら】
→レシカルボン坐剤
浣腸:便を直接柔らかくし、腸を刺激する
即効性を求める場合に使われる、液体状のお薬です。
グリセリン浣腸

出口でカチカチに固まってしまった便に、直接潤いを与えて柔らかくします。
同時に腸を刺激する作用もあり、注入後すぐに強い便意を感じることが多いです。あくまで緊急用として、連用は避けるべきお薬です。
【詳細はこちら】
→グリセリン浣腸
便秘に用いられる漢方薬
西洋薬が直接的な症状の緩和を目的とするのに対し、漢方薬は体全体のバランスを整え、「便秘になりにくい体質」を目指すのが得意です。
お腹の状態だけでなく、その人の体力や体質(漢方では「証(しょう)」と呼びます)に合わせて、オーダーメイドのように処方されます。
大建中湯(だいけんちゅうとう)

お腹を中からポカポカと温めて、弱った腸の動きを活発にしてくれるお薬です。
「お腹が冷たい」「ガスが溜まってお腹が張る」「お腹がグルグル鳴る」といった、冷えが原因で腸の元気がなくなっているタイプの便秘によく使われます。手術後の腸の回復を助ける目的で処方されることもあります。
【詳細はこちら】
→大建中湯
麻子仁丸(ましにんがん)

体に潤いを与えて、カチカチに硬くなった便に水分を含ませ、ツルンと出しやすくしてくれるお薬です。
「コロコロした便」が出る方に最適です。腸を潤す効果と、穏やかに排便を促す効果を併せ持っており、特にご高齢の方の便秘によく処方されます。
【詳細はこちら】
→麻子仁丸
防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

特に、お腹周りに脂肪が多く、体力があって食欲旺盛、のぼせやすい「がっちり・ぽっちゃりタイプ」の方に向いています。
体にこもった余分な熱や水分を外に出し、便通を整えることで、肥満や生活習慣病の改善も目指します。
【詳細はこちら】
→防風通聖散
六君子湯(りっくんしとう)

これは直接便を出すお薬ではなく、弱った胃腸の働きを元気にするお薬です。
「食欲がない」「すぐにお腹がいっぱいになる」「胃がもたれる」「疲れやすい」といった胃腸虚弱タイプの方の便秘に使われます。
【詳細はこちら】
→六君子湯
病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!
「処方薬が欲しいけど、やっぱり病院に行く時間がない…」 「体調が悪くて外出するのもつらい…」
そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。
オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。
保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!
\ オンライン診療の3つのメリット /
①自宅で完結、待ち時間ゼロ
予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。
24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!
診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。
薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。
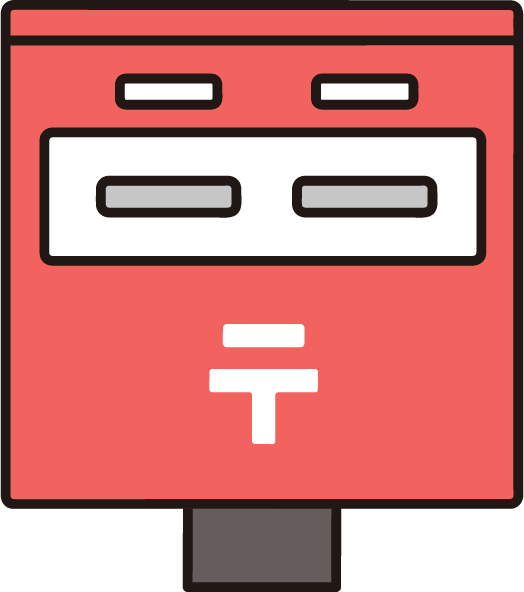
③感染リスクなし
病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。オンライン診療で専門治療を始めましょう!

処方薬の使い分け
これだけ種類があると「自分はどれなんだろう?」と思いますよね。
便秘治療には、実は基本的な「治療のステップ」があります。安全性の高い基本のお薬から始め、必要に応じてお薬を追加したり、種類を変えたりしていきます。
まずは「浸透圧性下剤」から
治療のスタート地点として、多くの場合酸化マグネシウム(マグミット)やモビコールといった浸透圧性下剤が選ばれます。
これらのお薬は腸を直接刺激せず、便に水分を集めるという自然に近い形で作用するため、お腹が痛くなりにくく、毎日続けても体が慣れてしまう「クセになる」心配がほとんどありません。
特に酸化マグネシウムは昔からの定番で幅広い便秘に有効ですが、モビコールは小さなお子さんや、腎臓の機能が少し心配なご高齢の方にも安心して使いやすいという利点があり、患者さん一人ひとりの背景に合わせて使い分けられます。
効果が不十分なら「上皮機能変容薬/胆汁酸トランスポーター(IBAT)阻害薬」
浸透圧性下剤を十分な量・期間使っても、「便が硬い」「スッキリ出ない」「お腹の張りが苦しい」といった場合に、アミティーザ、リンゼス、グーフィスといった新しいタイプの上皮機能変容薬を検討します。
これらのお薬は、腸からの水分分泌を促すことで、より強力に便を柔らかくしてくれます。
例えば、酸化マグネシウムを続けながらグーフィスを追加して腸の動きもサポートしたり、お腹の張りが特に強い方にはリンゼスに切り替えてみたりと、あなたの症状に合わせて治療法を強化・最適化していきます。
頓服での「刺激性下剤」
一方で、ラキソベロンやセンノシドといった刺激性下剤は、あくまで非常用としての役割です。毎日使うと腸がその刺激に慣れてしまい、自力で動く力が弱くなってしまう可能性があるためです。
「どうしても出ない」という時だけ頼るのが上手な使い方です。そのため、「3日以上出なかったら1回使う」といった具体的な指示と共に処方されることが多いです。
「出口」の悩みには「外用薬」(坐薬・浣腸)
便意を我慢しがちな方、いきむ力が弱いご高齢の方は、「便は出口まで来ているのに、硬くて出せない」という「直腸性便秘」がよく見られます。この場合、腸全体に効く飲み薬だけでは、解決しきれないことがあります。
そこで処方されるのが、レシカルボン坐剤やグリセリン浣腸といった外用薬です。出口で固まった便を直接柔らかくしたり、自然な便意を促したりして、スムーズな排便をピンポイントで助けてくれます。
もちろん、飲み薬で便全体を柔らかくしながら、出口のサポートとして坐薬を使う、といった併用もよく行われます。
このように、あなたの症状を丁寧に見極め、最適な治療法を段階的に考えます。
便秘薬の副作用と注意点
どんなお薬にも、効果という良い面と、副作用という注意すべき面があります。心配しすぎる必要はありませんが、正しく知っておくことで、より安心してお薬と付き合っていくことができます。
よくある副作用
下痢
便秘薬の副作用として最も多いのが、反対に便が緩くなりすぎてしまう「下痢」です。
特に、酸化マグネシウム(マグミット)やモビコール、アミティーザといった、便に水分を集めたり腸からの水分分泌を促したりするタイプのお薬でよく見られます。
これは、お薬が効きすぎているサインであり、ある意味では効果が出ている証拠とも言えます。ですが、日常生活に支障が出るほどの軟便や水様便が続く場合は、お薬の量が多すぎる可能性があります。
腹痛
ラキソベロンやセンノシドといった刺激性下剤を服用した際に、「お腹がギュルギュルと動く感じ」や、時には「差し込むような痛み」を感じることがあります。
これは、お薬が弱っていた腸を直接刺激して、ぜん動運動を活発にさせているために起こる痛みです。
排便があれば治まることがほとんどですが、痛みが我慢できないほど強い場合や、冷や汗、吐き気などを伴う場合は、すぐにお医者さんに相談しましょう。
高マグネシウム血症
酸化マグネシウム(マグミット)は非常に安全性の高いお薬ですが、ごくまれに注意が必要な副作用として「高マグネシウム血症」があります。
特に、腎臓の機能が低下しているご高齢の方などが注意すべき状態です。腎臓は、体内の余分なマグネシウムを尿として排出する役割があり、その機能が落ちていると、血液中のマグネシウム濃度が異常に高くなってしまうことがあります。
初期症状として、「吐き気」「立ちくらみ」「脈が遅くなる」「まぶたが重くなる」「手足の力が入らない」といったサインが現れることがあります。このような症状に気づいたら、すぐにお薬の服用を中止し、処方してくれた医療機関に連絡してください。
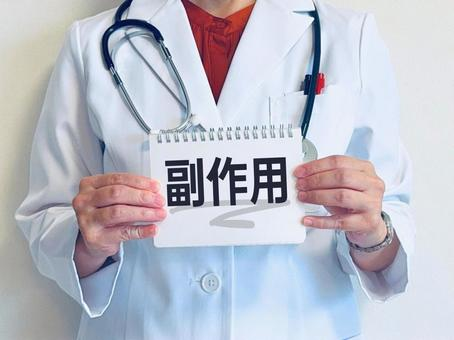
副作用に気づいたら
どんな副作用であっても、ご自身の判断でお薬の量を調整したり、中断したりしないでください。
「下痢が続くから、半分にする」「効かないから、倍量飲む」といった自己判断は、かえって体調を崩したり、治療がうまく進まない原因になります。
お医者さんや薬剤師さんにご自身の状態を相談し、どうすべきかを判断してもらいましょう。プロの視点であなたに合った一番良い方法を考えてくれます。
便秘薬のよくある質問(FAQ)
Q1. 処方されたお薬は、いつまで飲み続ければいいですか?

症状や便秘のタイプ、治療の目標によって様々です。まずは処方された日数分をしっかり飲み切りましょう。
「排便のリズムが整うまで」「生活習慣が改善するまで」など、お医者さんがあなたの状態を見ながら、お薬を減らしたり、やめたりするタイミングを判断してくれます。自己判断で中断せず、まずは医師の指示に従うことが大切です。
Q2. お薬が効かないときは、どうすればいいですか?
ご自身の判断でお薬の量を増やしたり、飲む回数を増やしたりするのは避けてください。効果が不十分な場合、「別のお薬に変える」「他の種類のお薬を組み合わせる」など、たくさんの次の手段があります。
まずは正直に「あまり効いている感じがしない」と伝えることが、あなたに合った治療法を見つけるための重要な一歩になります。
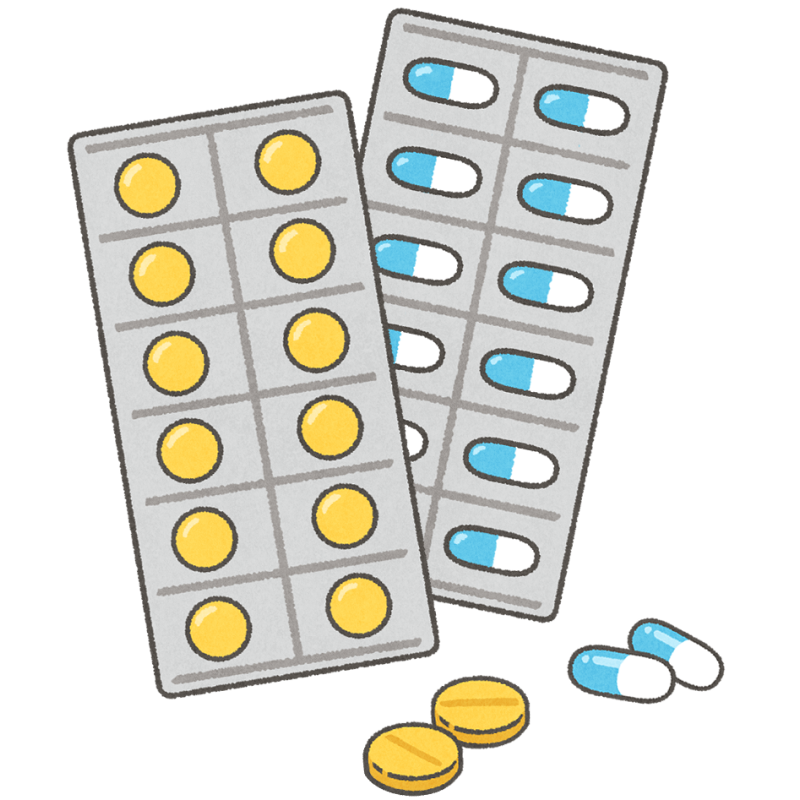
Q3. 便秘薬は、クセになったり依存したりしませんか?

酸化マグネシウムやモビコールといった「浸透圧性下剤」は、クセになる(依存性がある)心配はほとんどありません。
一方で、ラキソベロンなどの「刺激性下剤」は、毎日使い続けると腸が慣れてしまい、お薬がないと便が出にくくなる可能性があります。そのため、刺激性下剤は「頓服(とんぷく)」として処方するなど、安全に使えるように使い方を工夫が必要です。
Q4. 便秘で病院に行く場合、何科を受診すればいいですか?
まずはかかりつけの内科で相談するのが一般的です。より専門的な診察を希望する場合は、消化器内科や胃腸科を受診するとよいでしょう。
最近では、オンライン診療で気軽に専門医に相談することも可能になっています。

便秘の治療はウチカラクリニックオンライン診療へ!
便秘の改善には、この記事でご紹介した食事や運動といったセルフケアが基本となります。しかし、それでも改善しないつらい便秘には、医師が処方する様々なお薬が頼りになります。
「市販薬を色々試したけど、スッキリしない…」
「仕事が忙しくて、『便秘ごとき』で病院に行くのは気が引ける…」
そんなときは、通院の手間なく専門医に相談できるウチカラクリニックのオンライン診療が便利です。
- スマホやPCがあれば、全国どこからでも受診可能
- 対面診療と料金は変わらず、安心してご利用いただけます
- お忙しい方でも安心の年中無休で診療
- 薬は郵送or近くの薬局で受け取り可能
通院の時間や手間をかけずに、ご自身の症状や体質に合った薬を専門医に相談し、スムーズにお薬を受け取ることが可能です。一人で悩まず、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
つらい便秘や下痢は
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
内科のオンライン診療
この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師
森 勇磨
経歴
東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)
YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。