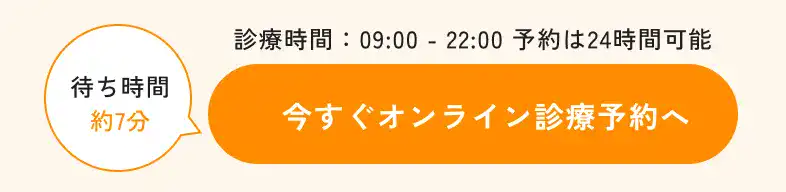急な高熱や全身の倦怠感…。「インフルエンザかも?」と診断されたら、「仕事は何日休む?」「子どもはいつから登校できる?」と気になりますよね。
インフルエンザの休み期間は基準が少し複雑で、自己判断は感染を広げてしまう恐れがあります。
この記事では、公的な情報に基づき、正しい休み期間の基準、日数の数え方、そして家族が感染した場合の対応まで医師が徹底解説。あなたの疑問をすべて解決し、安心して療養できるようサポートします。
インフルエンザの治療なら
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
発熱外来(コロナ・インフルエンザ・風邪など)のオンライン診療
目次
インフルエンザとは?普通の風邪との違い
まず、インフルエンザの基本的な知識と、風邪との違いについて確認しておきましょう。
インフルエンザは、「インフルエンザウイルス」に感染することで起こる急性の呼吸器感染症です。一般的な風邪(感冒)としばしば混同されますが、症状の現れ方や重症度に大きな違いがあります。
| 項目 | インフルエンザ | 普通の風邪 |
|---|---|---|
| 原因 | インフルエンザウイルス | ライノウイルス、コロナウイルスなど様々 |
| 発症 | 急激 | ゆるやか |
| 主な症状 | 38℃以上の高熱、頭痛、強い倦怠感、筋肉痛・関節痛など全身症状が強い | 喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳など喉や鼻の症状が中心 |
| 重症化リスク | 高い(肺炎、脳症などを合併することも) | 低い |
| 流行時期 | 主に冬期(12月~3月) | 通年 |
このように、インフルエンザは普通の風邪に比べて症状が重く、感染力も非常に強いのが特徴です。そのため、感染を広げないように、法律や社会的なルールとして「休み期間」の基準が設けられています。
詳しいインフルエンザの解説はこちらの記事をチェック!
→それ、風邪じゃなくインフルエンザかも?症状チェックと薬や検査を医師が解説!
インフルエンザで休む期間の基準
インフルエンザで休むべき期間は、法律(学校保健安全法)で明確に定められています。
多くの企業でもこの基準が準用されており、これが社会的なコンセンサスとなっています。
インフルエンザの休み期間(出席停止期間)
「発症した後5日を経過し、
かつ、
解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」
※この2つの条件を両方とも満たす必要があります。
どちらか一方だけを満たしても、登校や出社はできません。
例えば、熱がすぐに下がったとしても、発症から5日間はウイルスを排出する可能性があるため、自宅療養が必要です。
【こちらの記事もチェック】
インフルエンザの潜伏期間は?発症前でもうつる?感染力のピーク・期間・治るまでの日数を医師が解説!
正しい休み期間の数え方
この基準で最も間違いやすいのが「日数の数え方」です。
正しい数え方のポイントは2つです。
- 症状が出た日(発症日)を「0日目」として数える
- 解熱剤などを使わずに平熱になった日を「解熱0日目」とする
具体例で見てみましょう。
【月曜に発症し、水曜に解熱した小学生の場合】
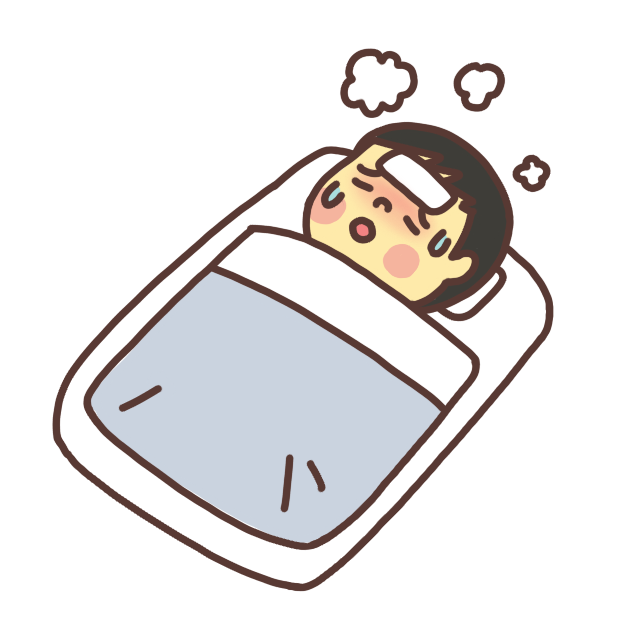
- 月曜日: 発熱(発症日 0日目)
- 火曜日: 発症後1日目
- 水曜日: 解熱(解熱 0日目)/ 発症後2日目
- 木曜日: 解熱後1日目 / 発症後3日目
- 金曜日: 解熱後2日目 / 発症後4日目
- 土曜日: 【条件1】発症後5日経過 / 解熱後3日目
- 日曜日: 登校・外出可能
このケースでは、「解熱後2日」は金曜日に満たしますが、「発症後5日」の条件を満たしていません。
両方の条件を満たすのは土曜日いっぱいとなるため、登校できるのは日曜日からとなります。
「隔離期間」と「待機期間」の違いは?
インフルエンザの情報を調べる中で、「隔離期間」や「待機期間」という言葉を目にすることがあるかもしれません。この2つの言葉は混同されがちですが、意味も対象となる人も全く異なります。
隔離期間:ウイルスを排出している「感染者本人」が対象
「隔離期間」とは、インフルエンザと診断された感染者ご本人が、ウイルスを周囲にうつさないようにするために自宅などで療養する期間のことです。
この記事で解説している「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」という出席停止・出勤停止の基準が、まさにこの「隔離期間」にあたります。
ウイルスを体外に排出している可能性がある間、他者との接触を避けるための重要な措置です。
待機期間:感染の可能性がある「濃厚接触者」が対象
一方、「待機期間」とは、感染者と接触したことで感染している可能性がある方(濃厚接触者)が、症状が出ないかをご自身で観察する期間を指します。いわゆる「健康観察期間」です。
ただし、現在の日本の制度では、インフルエンザの濃厚接触者に対して法律で定められた一律の「待機期間」はありません。
ご家族がインフルエンザになっても、ご自身に症状がなければ基本的には出勤や登校が可能です。しかし、インフルエンザには約1~3日の潜伏期間があるため、その間はご自身の体調変化に注意深く気を配り、マスク着用や手洗いといった感染対策を徹底することが求められます。

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!
「処方薬が欲しいけど、やっぱり病院に行く時間がない…」 「体調が悪くて外出するのもつらい…」
そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。
オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。
保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!
\ オンライン診療の3つのメリット /
①自宅で完結、待ち時間ゼロ
予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。
24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!
診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。
薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。
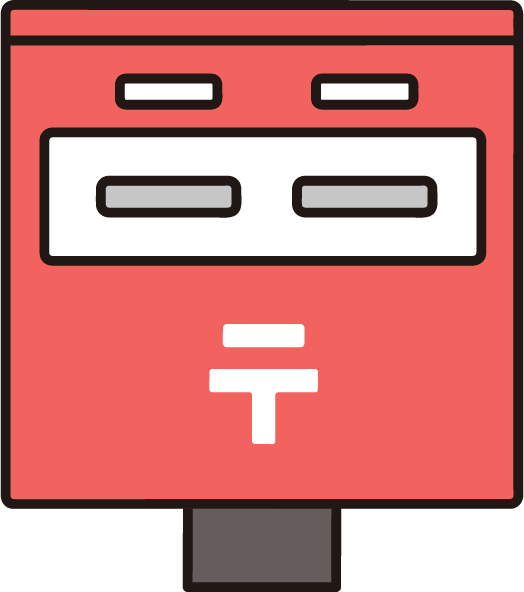
③感染リスクなし
病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。オンライン診療で専門治療を始めましょう!

【子供/学生】学校の出席停止期間について
幼稚園児や小・中・高校生の場合、インフルエンザは「学校保健安全法施行規則」によって出席停止期間が定められています。これは、学校内での集団感染を防ぐための非常に重要な措置です。
- 基準: 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」
- 幼児の注意点: 小学生以上と異なり、幼児(未就学児)は解熱後の待機期間が「3日間」と長くなっています。これは、幼児の方がウイルスを排出する期間が長い傾向にあるためです。
インフルエンザと診断されたら、速やかに学校へ連絡しましょう。
登校を再開する際には、学校によっては医師が記入した「治癒証明書」や「登校許可証」の提出が必要な場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
ウチカラクリニックでも、インフルエンザに罹ったことを証明する「診断書」の発行、「治癒証明書」や「登校許可証」などの発行が可能です!
【大人/社会人】会社の出勤停止期間の目安
社会人の場合、実は学校保健安全法のような法律による一律の出勤停止義務はありません。
しかし、多くの企業では感染拡大防止の観点から、この法律の基準(発症後5日かつ解熱後2日)を目安として就業規則に定めています。
インフルエンザと診断された社会人が取るべき行動は以下の通りです。
- 速やかに会社(上司)に報告する
- 自社の就業規則を確認する
※「感染症」や「病気休暇」などの項目をチェック - 会社の指示に従う
自己判断で「熱が下がったから」と出社することは絶対に避けてください。
周囲への感染リスクはもちろん、体力が回復していない状態で無理をすると、症状が悪化する可能性もあります。会社によっては診断書の提出を求められることもあるため、あわせて確認しましょう。
ウチカラクリニックでも、インフルエンザに罹ったことを証明する「診断書」の発行、「治癒証明書」などの発行が可能です!
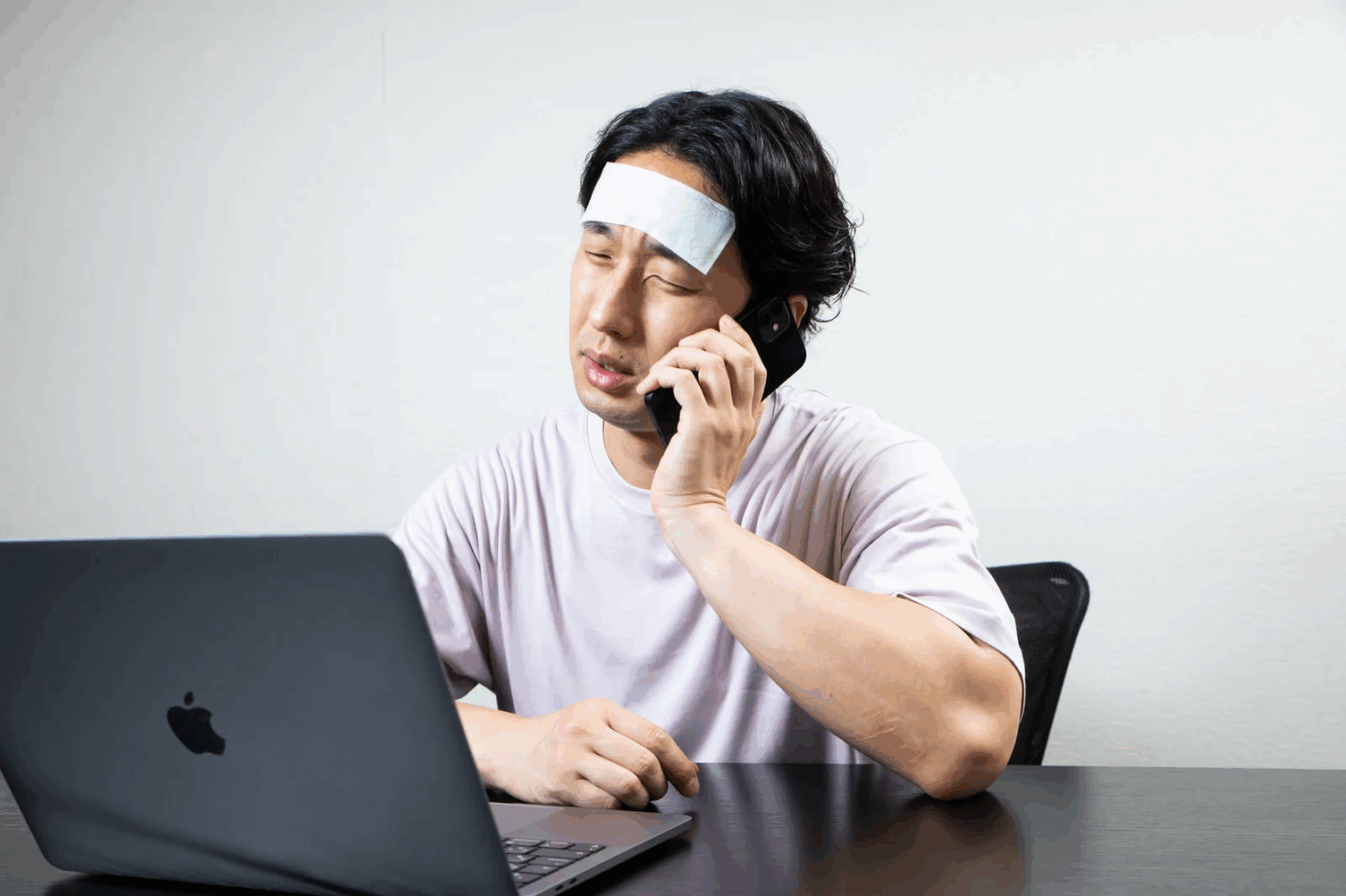
家族がインフルエンザに感染した場合、自分は休むべき?【濃厚接触者】
ご家族がインフルエンザに感染した場合、「自分は濃厚接触者になるけど、仕事や学校はどうすれば?」と不安になりますよね。
同居家族がインフルエンザになっても、ご自身に症状がなければ、法律上、会社や学校を休む義務はありません。基本的には、通常通り出勤・登校が可能です。
しかし、以下の点を必ず理解しておきましょう。
潜伏期間を意識
インフルエンザの潜伏期間は約1~3日です。今は症状がなくても、すでにウイルスに感染している可能性は十分に考えられます。
所属先の方針を必ず確認する
職場によっては、独自のルールを設けている場合があります。
特に、医療機関、介護施設、保育所など、感染が重症化につながりやすい方と接する職場では、数日間の自宅待機や検温の義務付けなどを指示されることがあります。必ず上司や学校に家族の状況を報告し、指示を仰いでください。
期間中に徹底すべき感染対策
症状がない場合でも、周囲への配慮として普段以上の感染対策を徹底しましょう。

- 不織布マスクを常に着用する
- こまめな手洗い、手指消毒を徹底する
- 定期的に室内の換気を行う
- 少しでも体調に変化があれば、無理せず休む
ご自身の体調を注意深く観察し、喉の痛みや倦怠感、微熱などの初期症状が見られた場合は、すぐに出勤・登校を控え、医療機関を受診しましょう。
療養・待機期間中の過ごし方と家庭内での感染対策
隔離期間中は、ご自身の体を回復させることと、家族など同居する人への感染を防ぐことが重要です。
療養に専念する
- とにかく安静にし、十分な睡眠をとる
- 脱水症状を防ぐため、こまめに水分補給をする(経口補水液、スポーツドリンクなど)
- 消化が良く栄養のあるものを食べる(おかゆ、うどん、スープなど)
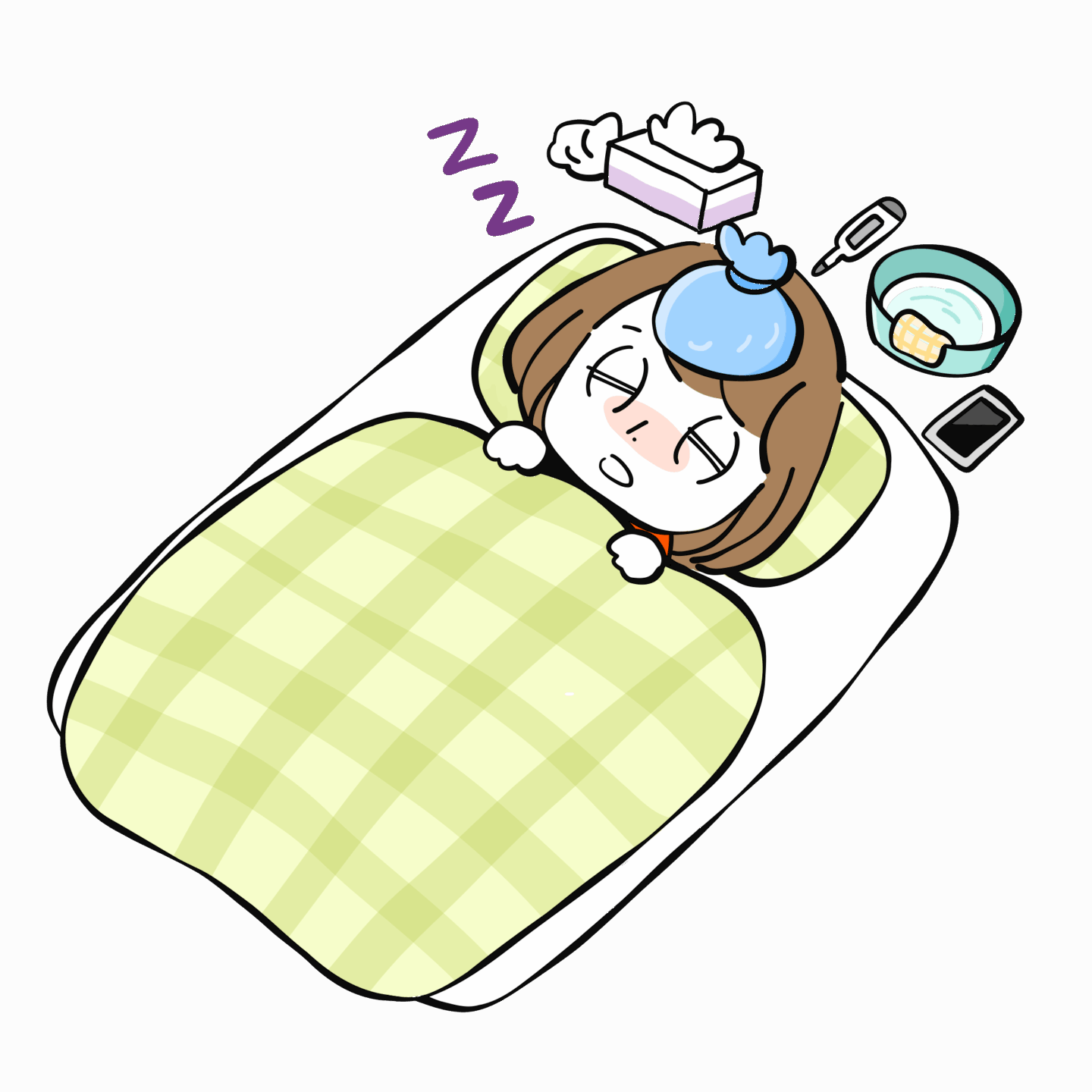
家庭内感染を防ぐ
- できるだけ部屋を分け、療養する人と家族の接触を減らす
- 1~2時間おきに部屋の換気を行う
- 患者本人も家族もマスクを着用する
- こまめに石鹸で手洗いをする
- タオルや食器の共用は避ける
- ドアノブやテーブルなど、よく触る場所をアルコールで消毒する
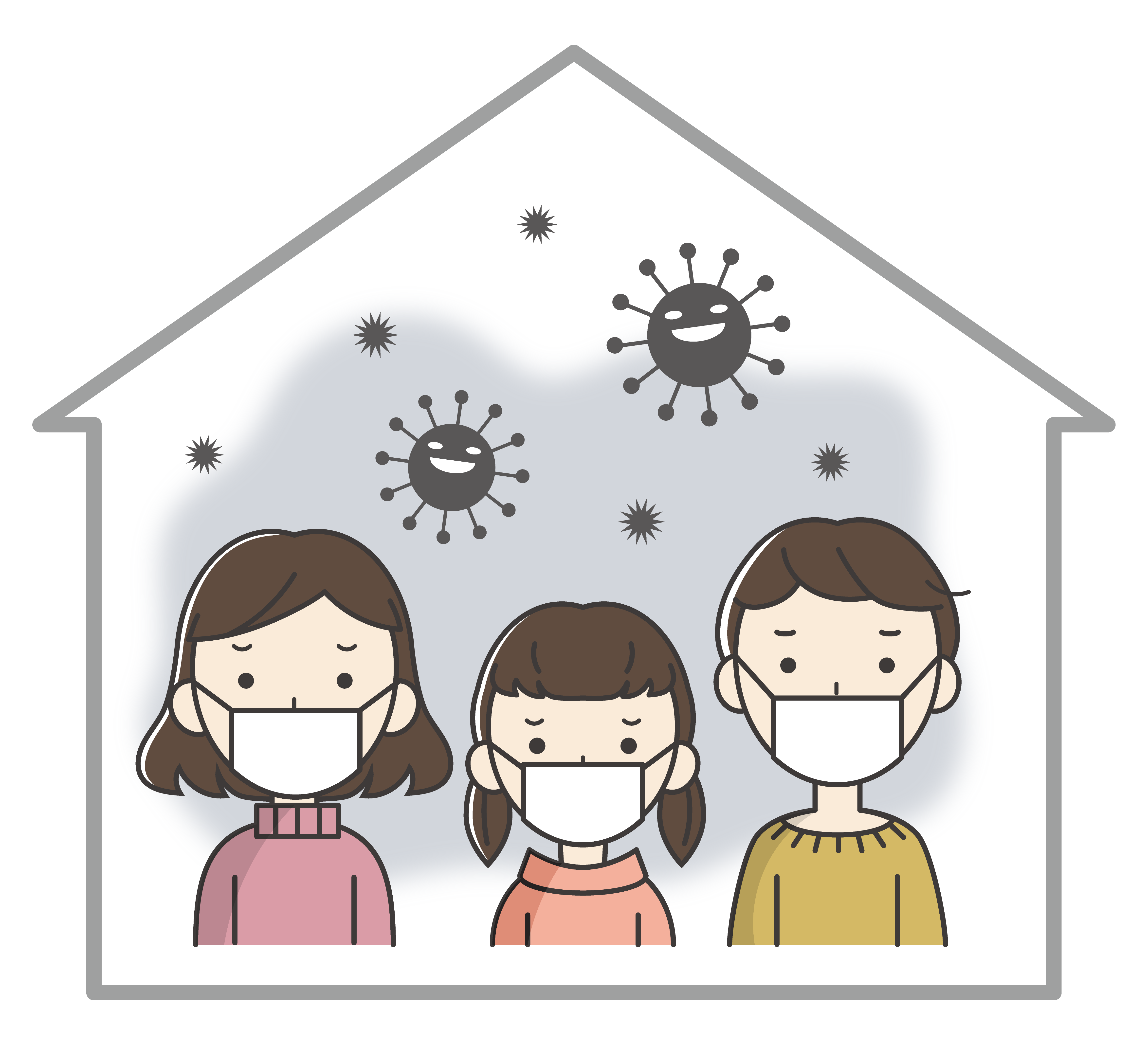
インフルエンザの待機・隔離期間に関するQ&A
会社や学校に提出する診断書はいつ貰えばいいですか?
診断を受けたその日に依頼するのが最もスムーズです。
医師にインフルエンザと診断された際に、「会社(または学校)に提出する診断書をお願いします」と伝えましょう。後日、電話などで発行を依頼することも可能な場合がありますが、再度来院が必要になったり、医療機関によっては対応が異なったりするため、最初の受診時に確認・依頼するのが確実です。
なお、診断書の発行は通常、別途費用がかかります。
【診断書について詳しい解説はこちら】
病院で貰える診断書の費用は?どんな時にもらうの?もらい方などを医師が解説!
インフルエンザだと嘘をついて会社を休んだらバレますか?
バレる可能性は非常に高く、リスクも大きいため絶対にやめるべきです。
多くの企業では、数日以上休む場合に医師の診断書の提出を義務付けています。診断書を偽造すれば、有印私文書偽造罪という犯罪に問われる可能性があります。
また、傷病手当金の申請などを行うと、健康保険組合から医療機関へ受診の事実確認が行われることもあります。
安易な嘘は、最終的にご自身の職場での信用を完全に失うことにつながります。本当に心身の不調で休みが必要な場合は、正直に会社に相談することが最善の道です。
インフルエンザで休む場合、有給休暇扱いになりますか?
ご自身の「年次有給休暇(有給)」を使って休むのが一般的です。会社独自の「病気休暇」制度が利用できる場合もありますが、それが有給か無給かは就業規則によります。
有給休暇を使い切っている場合は「欠勤(無給)」扱いになることもあります。給与が支払われない場合でも、健康保険から「傷病手当金」が支給される制度もありますので、まずは会社の就業規則を確認し、上司や人事部に相談するのが確実です。
【傷病手当金について詳しい解説はこちら】
傷病手当金ってなに?休職中もお金がもらえる?支給の条件や申請書について医師が解説!
咳だけがしつこく残っています。出社・登校してもいいですか?
インフルエンザの出席停止・出勤停止の基準を満たしていれば、基本的には可能です。
一般的に、熱が下がり数日経てばウイルスの排出量も大きく減り、他者へ感染させるリスクは低いとされています。
ただし、咳が残っている間は、周りの方への配慮として必ずマスクを着用しましょう。また、長引く咳は体力が完全に戻っていないサインでもあります。無理をせず、体調を最優先に行動してください。
予防接種を打っていても休み期間は短くなりますか?
いいえ、休み期間の基準は変わりません。
インフルエンザワクチンは、感染後の「重症化」を防ぐことが主な目的です。感染を100%防ぐものではなく、感染した場合のウイルス排出期間を短くする保証もありません。
そのため、予防接種の有無にかかわらず、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)」という基準を守る必要があります。
【詳しい解説はこちら】
インフルエンザワクチンの予防接種はいつがいい?費用・効果・副反応を医師が解説!
インフルエンザA型とB型で休み期間は変わりますか?
変わりません。ウイルスの型によって症状の傾向に違いはありますが、出席停止や出勤停止の期間に関する基準は同じです。
【診断書について詳しい解説はこちら】
インフルエンザA型とB型の違いは?症状・流行時期・潜伏期間を医師が解説【C型もあるの?】
解熱剤で熱が下がった場合も「解熱」に含まれますか?
いいえ、含まれません。ここでの「解熱」とは、解熱剤などの薬の力を使わずに、本人の免疫力で平熱が続いている状態を指します。薬の効果が切れた後の体温で判断してください。
検査で陰性でしたが、症状はインフルエンザっぽいです。どうすれば?
偽陰性(ぎいんせい)の可能性もあります。インフルエンザの検査は、発症からの時間が短いとウイルス量が少なく、陽性反応が出ないことがあります。症状が続く場合は、自己判断せず医師の指示に従い、必要であれば再度受診しましょう。
インフルエンザの治療はウチカラクリニックオンライン診療へ!
インフルエンザは多くの方が経験する病気だからと、「これくらいなら大丈夫だろう」と無理をしてしまう人が少なくありません。「急な高熱」や「つらい関節痛」といった症状は、体からの重要なSOSサイン。このサインを見逃さず、適切な期間しっかり休むことが、回復への一番の近道であり、周囲への感染拡大を防ぐための大切なマナーです。
「高熱で病院の待合室に行くこと自体がつらい…」
「会社や学校に提出する診断書がすぐに欲しい」
「家族がインフルエンザで、外出せずに相談したい」
そんな方には、ウチカラクリニックのオンライン診療がおすすめです。
- スマホやPCがあれば、つらい体で外出せず自宅から受診可能
- インフルエンザの治療薬をご自宅近くの薬局、または郵送で受け取れる
- お仕事や学校の提出に必要な診断書もオンラインで発行
- お忙しい方でも安心の年中無休で診療
つらい症状を我慢して無理に出勤・登校したり、回復が遅れてしまったりする必要はもうありません。あなたのライフスタイルに寄り添いながら、症状の早期回復と、必要な手続き(診断書の発行など)をスムーズに進める方法を、専門の医師と一緒に見つけていきましょう。
インフルエンザの治療なら
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
発熱外来(コロナ・インフルエンザ・風邪など)のオンライン診療
この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師
森 勇磨
経歴
東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)
YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。