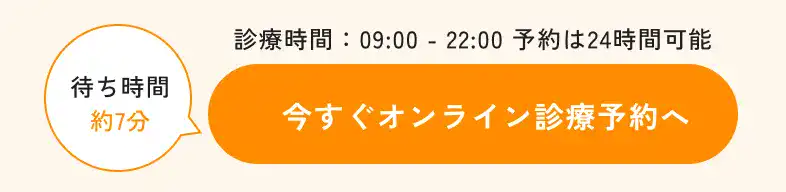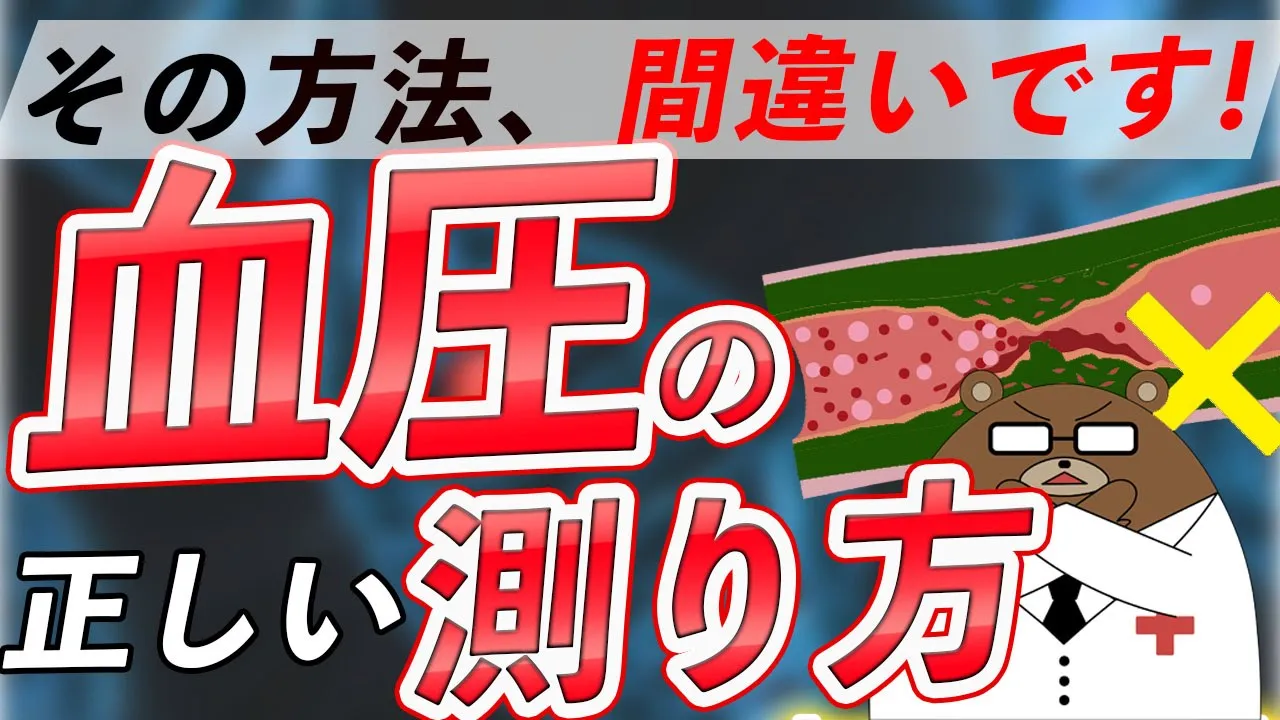「繰り返すてんかん発作をなんとかしたい…」「気分の波が激しくてつらい…」「片頭痛が頻繁に起きて、日常生活に困っている…」そんな、様々なお悩みに対して、お医者さんから「バルプロ酸」というお薬が処方されることがあります。
「バルプロ酸って、どんなお薬なんだろう?」「副作用はあるの?」「妊娠中でも大丈夫?」など、たくさんの疑問や不安を感じるかもしれませんね。
この記事では、脳の神経の興奮を鎮める働きのあるお薬「バルプロ酸」について、その正体から効果、副作用、そして何よりも大切な正しい飲み方や注意点を、医師がとことん優しく、そして分かりやすく解説します!バルプロ酸と上手に付き合って、つらい症状をコントロールし、穏やかな毎日を目指しましょう。
ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。
(全国からご自宅で受診可能です。)
片頭痛などの頭痛にお悩みの方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。
診療時間:09:00 – 22:00
予約は24時間可能!
目次
バルプロ酸とは?効果は?
バルプロ酸は、脳の神経細胞の過剰な興奮を抑えることで、様々な効果を発揮する飲み薬です。「バルプロ酸ナトリウム」というのが正式な成分名で、てんかんの治療薬として長く使われてきた実績があります。
しかし、その働きはてんかんだけでなく、気分の波を安定させる効果(躁状態の治療)や、片頭痛の発作を予防する効果もあることが分かり、現在ではこれらの症状の治療にも広く用いられています。
バルプロ酸は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えたり、神経細胞の膜を安定させたりすることで、その効果を発揮すると考えられています。ただし、その作用は多岐にわたるため、全てが完全に解明されているわけではありません。
バルプロ酸の成分
バルプロ酸の主役は、「バルプロ酸ナトリウム」という成分です。
では、このバルプロ酸ナトリウムは、私たちの脳の中でどんな風に働いて、てんかん発作や気分の波、片頭痛を抑えてくれるのでしょうか?少し専門的になりますが、主な働きをできるだけ簡単に説明しますね。
①脳の興奮をクールダウンさせるブレーキ役を増やす
脳の中には、神経の興奮を伝えるアクセル役の物質(興奮性神経伝達物質)と、興奮を抑えるブレーキ役の物質(抑制性神経伝達物質)があります。バルプロ酸は、このブレーキ役の代表である「GABA(ギャバ)」という物質の脳内濃度を高めたり、GABAの働きを強めたりすると考えられています。これにより、脳全体の過剰な興奮が鎮まりやすくなります。
②神経細胞の膜を安定させる盾になる
神経細胞は、電気的な信号をやり取りして情報を伝えていますが、この信号のやり取りが過剰になると、てんかん発作などが起こりやすくなります。バルプロ酸は、神経細胞の膜に働きかけて、この電気的な興奮が過度に起こらないように、いわば「盾」のような役割をしてくれると考えられています。
③その他の作用
この他にも、カルシウムイオンやナトリウムイオンといった、神経細胞の興奮に関わるイオンの流れを調整する作用なども報告されており、これらの複数の作用が組み合わさって効果を発揮すると考えられています。
このように、バルプロ酸は、脳の神経活動を多方面から穏やかにすることで、様々な症状を改善へと導きます。
バルプロ酸の効果
- 各種てんかん発作(全般発作、部分発作など)を予防・抑制する
- 躁病および躁うつ病の躁状態の症状(気分の高揚、活動性の亢進、多弁など)を改善する
- 片頭痛発作の発症を抑制する(予防効果)
重要なのは、片頭痛に対しては「発作が起きてしまったときの痛みをすぐに取るお薬」ではなく、「そもそも発作が起きにくくするためのお薬(予防薬)」であるという点です。
どんなときに使う?(適応疾患・部位)
- 各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害(不機嫌、易怒性など)の治療
- 躁病および躁うつ病の躁状態の治療
- 片頭痛発作の発症抑制
てんかんに対しては、小さなお子さんから大人まで幅広く使われます。躁状態に対しては、気分の波を穏やかにするために用いられます。片頭痛予防としては、他の予防薬で効果が不十分だった場合や、特定のタイプの片頭痛に考慮されることがあります。
バルプロ酸の種類
バルプロ酸のお薬には、患者さんの状態や飲みやすさに合わせて、いくつかのタイプ(剤形)があります。
バルプロ酸ナトリウム錠/細粒(普通製剤)
一般的な錠剤や、水に溶かして飲むことができる細粒タイプです。1日に2~3回に分けて服用することが多いです。
代表的な商品名: デパケン®錠、デパケン®細粒など
バルプロ酸ナトリウム徐放錠/徐放顆粒(ゆっくり効くタイプ)
「徐放(じょほう)」とは、お薬の成分が体の中でゆっくりと時間をかけて溶け出し、効果が長く続くように工夫された製剤のことです。「R」という文字が薬の名前についていることが多いです。
これにより、1日の服用回数を減らしたり(例えば1日1回や2回)、血中濃度(血液中のお薬の濃度)の変動を小さくして副作用を軽減したりする効果が期待できます。
徐放錠は、噛んだり砕いたりせずに、そのまま水やぬるま湯で服用してください。割線が入っていて半分に割れるタイプもありますが、それ以外はそのまま飲むのが基本です。
代表的な商品名: デパケン®R錠、セレニカ®R錠、セレニカ®R顆粒など
バルプロ酸ナトリウムシロップ
甘い味がついた液体のお薬で、小さなお子さんや錠剤・カプセルが飲みにくい方に使われます。
代表的な商品名: デパケン®シロップなど
バルプロ酸の使い方(用法・用量)
バルプロ酸を飲む量や回数は、治療する病気の種類、年齢、体重、症状の重さなどによって、一人ひとり細かく調整されます。必ず医師や薬剤師の指示に従って服用してくださいね。
- てんかんの治療: 通常、1日400~1200mgを2~3回に分けて服用します。
- 躁状態の治療: 通常、1日400~1200mgを2~3回に分けて服用します。
- 片頭痛発作の予防: 通常、1日400~800mgを1日2回に分けて服用します。最大で1日1000mgまでとされることもあります。
バルプロ酸の副作用
主な副作用
比較的よくみられる副作用
- 眠気、ふらつき、めまい、頭痛
- 消化器症状(吐き気、嘔吐、食欲不振または食欲増進、胃の不快感、便秘、下痢など)
- 手の震え(振戦)
- 体重増加
- 脱毛(一時的なことが多いです)
- 血液検査値の異常(肝機能障害、血小板減少、高アンモニア血症など): 定期的な血液検査でチェックすることが大切です。
ごくまれだけど注意が必要な副作用
- 重篤な肝障害: 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、全身倦怠感、食欲不振、吐き気などが現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。特に飲み始めの6ヶ月以内や、小さなお子さん、複数の抗てんかん薬を併用している場合に注意が必要です。
- 高アンモニア血症を伴う意識障害: 意識がぼんやりする、反応が鈍くなるなどの症状が現れます。
- 膵炎(すいえん): 激しい腹痛、背中の痛み、吐き気などが現れます。
- 血液障害(再生不良性貧血、赤芽球癆、汎血球減少、重篤な血小板減少など): あざができやすい、鼻血が出やすい、熱が続く、のどが痛いなどの症状に注意が必要です。
- 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(TEN): 高熱、目の充血、口や陰部のただれ、全身の赤い発疹や水ぶくれなどが現れる非常に重い皮膚障害です。
- 過敏症症候群: 発疹、発熱、リンパ節の腫れなどが現れます。
副作用が出たときの対処法
- 眠気やふらつき: バルプロ酸を飲んでいる間は、自動車の運転や危険な機械の操作、高所での作業などは避けるようにしましょう。
- 消化器症状: 症状が軽い場合は様子を見ることが多いですが、つらい場合や長引く場合は医師に相談しましょう。食後に飲む、徐放錠に変更するなどで和らぐこともあります。
- 体重増加や脱毛: 気になる場合は医師に相談してください。食事療法や他の対策を一緒に考えてくれることがあります。
いつもと違う体調の変化を感じたり、副作用が長引いたりする場合や重篤な副作用のサインに気づいたら、直ちに服用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。
バルプロ酸の注意事項・禁忌
バルプロ酸は比較的安全性の高いお薬とされていますが、安全に使うためにはいくつか注意点があり、使ってはいけない方もいます。
使ってはいけない方
絶対に使ってはいけない方(禁忌)
- 重い肝臓の病気のある方、またはその既往歴のある方
- 本剤の成分に対し過敏症(アレルギー)の既往歴のある方
- 尿素サイクル異常症の患者: 高アンモニア血症を引き起こし、重篤な意識障害に至ることがあります。
- 妊娠中の方、または妊娠している可能性のある女性(ただし、てんかんの治療で他の治療法がない場合に限り、慎重に考慮されることがあります):胎児への影響(催奇形性など)のリスクがあるため、原則禁忌に近い非常に慎重な扱いが必要です。
使うときに特に注意が必要な方
- 肝臓や腎臓の機能が低下している方
- 血液の病気のある方、またはその既往歴のある方
- 薬物過敏症の既往歴のある方
- 高齢者・小さなお子さん(特に2歳未満): 重篤な肝障害のリスクが高いため、特に慎重な投与が必要です。
併用に注意が必要な薬
- カルバペネム系抗生物質(メロペン®、フィニバックス®など): バルプロ酸の血中濃度を著しく低下させ、てんかん発作が再発するおそれがあるため、原則として併用禁忌です。
- 一部の抗てんかん薬(フェニトイン、フェノバルビタール、カルバマゼピン、ラモトリギンなど): 互いに作用を強めたり弱めたりすることがあります。
- アスピリン(高用量の場合): バルプロ酸の作用を強めることがあります。
- ワルファリン(血液をサラサラにするお薬): 作用を強めることがあります。
- 一部の抗うつ薬、抗精神病薬
上記以外にも多数のお薬と相互作用を起こす可能性があります。他に飲んでいるお薬やサプリメントがある場合は、必ず医師や薬剤師に伝えましょう。
使用上の注意
急にやめると、てんかん発作が再発したり、症状が悪化したりする危険性があります。自己判断で量を増やしたり減らしたり、急にやめたりしないようにしましょう。特に予防目的で使う場合は、効果を実感できるまでに時間がかかることがあります。
バルプロ酸は、効果を発揮しやすく、かつ副作用を抑えるために、血液中のお薬の濃度を適切な範囲に保つことが重要です。そのため、定期的に血液検査をして、血中濃度をチェックしながら服用量を調整することがあります。
妊娠を希望する場合や妊娠が判明した場合は、すぐに医師に相談してください。
保管方法
- 直射日光・高温多湿を避けて保管しましょう。
- 子どもの手の届かない場所に置いてください。
飲み忘れたら?
飲み忘れたことに気づいたら、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は(例えば、1日2回服用の場合で、次の服用まで4~5時間以内など)、忘れた分は飲まずに、次の時間に1回分だけ飲みましょう。
絶対に2回分をいっぺんに飲んではいけません。
バルプロ酸に市販薬はある?値段は?
市販薬
「バルプロ酸」と同じ有効成分「バルプロ酸ナトリウム」を含む市販薬は、現在のところありません。
バルプロ酸は、医師の診断と処方、そして定期的な経過観察が必要な薬です。
てんかんや躁状態、片頭痛の予防といった症状でお困りの場合は、自己判断で市販薬を探すのではなく、必ず医療機関を受診して、専門医に相談するようにしてください。
ジェネリック名
バルプロ酸の有効成分「バルプロ酸ナトリウム」を含むジェネリック医薬品(後発医薬品)も、錠剤、徐放錠、細粒、シロップなど各剤形で多数販売されています。
先発医薬品としてデパケン、デパケンR、バレリン、セレニカRがあります。
後発品(ジェネリック)は「バルプロ酸ナトリウム錠「〇〇」」や「バルプロ酸ナトリウム徐放錠「〇〇」」といった名称で、一般的に先発医薬品(デパケン、セレニカなど)よりも薬価が安価なことが多いです。
薬価
時期や規格によって金額は変わってきますが、以下のような目安です。
- デパケンR錠100mg:10.4円/錠
- デパケンR錠200mg:11.3円/錠
- バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」:12.3円/錠
- デパケン細粒40%:19.7円/g
- バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」:25.9円/g
- デパケンシロップ5%:7.9円/mL
- バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」:9.3円/mL
- セレニカR錠200mg:10.9円/錠
- セレニカR錠400mg:17.4円/錠
- セレニカR顆粒40%:36.7円/g
※2025年4月29日現在
※薬価は改定などで変わる可能性があります。
添付文書
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」/バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」/バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」/バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」
よくある質問(FAQ)
Q. バルプロ酸はどんな病気に使われるの?
バルプロ酸は、主にてんかんの発作を抑えるため、躁病や躁うつ病の躁状態(気分の高ぶりなど)を鎮めるため、そして片頭痛の発作を予防するために使われます。脳の神経の興奮を穏やかにする働きがあります。
Q. 妊娠中でも使える?
バルプロ酸は、妊娠中に服用すると、胎児に先天的な異常(催奇形性)を引き起こすリスクが他のお薬よりも高いことが知られています。また、生まれてくるお子さんの発達に影響を与える可能性も指摘されています。そのため、原則として妊娠中の服用は避けるべきお薬です。
Q. 授乳中でも使える?
バルプロ酸の成分は母乳中に移行しますが、その量は比較的少ないとされています。しかし、赤ちゃんへの影響が全くないとは言い切れないため、授乳中に服用する場合は医師に相談し、指示に従ってください。
Q. 小児でも使える?
バルプロ酸はてんかんの治療などで、小さなお子さんにも使われることがあります。シロップ剤や細粒、小児用の徐放顆粒など、お子さんが飲みやすい剤形も用意されています。ただし、特に2歳未満のお子さんでは、重篤な肝障害のリスクが成人よりも高いため、非常に慎重な投与と経過観察が必要です。
Q. バルプロ酸を飲んだら運転しても大丈夫?
バルプロ酸を服用すると、副作用として眠気、ふらつき、めまい、集中力の低下などが現れることがあります。そのため、バルプロ酸を飲んでいる間は、自動車の運転や危険を伴う機械の操作、高所での作業などは避けるようにしてください。
Q. バルプロ酸は飲んでからどのくらいで効き始めますか?
効果が現れるまでの時間や実感の仕方は、治療する病気の種類や患者さんによって異なります。
①てんかんの予防: 数日~数週間で徐々に発作が起こりにくくなることが多いです。安定した効果が得られるには、血中濃度を見ながら量を調整していくため、もう少し時間がかかることも。
②躁状態の改善効果: 数日~1週間程度で、気分の高ぶりなどが少しずつ落ち着いてきます。
③片頭痛の予防効果: 1~2ヶ月程度、あるいはそれ以上かかることがあります。
すぐに効果が出なくても、医師の指示通りに根気よく続けることが大切です。
Q. バルプロ酸を飲んでいるときにお酒を飲んでも大丈夫?
バルプロ酸を服用中にお酒(アルコール)を飲むと、眠気やふらつきなどの副作用が強く現れる可能性があります。また、アルコールは肝臓に負担をかけるため、バルプロ酸による肝機能への影響を増強させてしまうおそれもあります。
Q. 「バルプロ酸を飲むと太る」って聞いたけど本当ですか?
はい、バルプロ酸の副作用の一つとして、体重増加が報告されています。頻度はそれほど高くありませんが、一部の方に見られることがあります。原因としては、食欲が増進したり、代謝に影響したりすることなどが考えられていますが、はっきりとしたメカニズムは完全には分かっていません。
Q. バルプロ酸は急にやめても大丈夫?
バルプロ酸を自己判断で急にやめるのは非常に危険です。 特に、てんかんの治療で服用している場合、急に中断すると、てんかん発作が頻発したり、重積状態(発作が止まらなくなる危険な状態)になったりするおそれがあります。また、躁状態や片頭痛の予防で服用している場合も、症状が悪化したり、離脱症状が現れたりすることがあります。
まとめ
今回は、てんかん、躁状態、そして片頭痛の予防など、幅広いお悩みに使われるお薬「バルプロ酸」について、詳しく見てきました。
バルプロ酸は、脳の神経の過剰な興奮を穏やかにすることで、様々な症状を改善してくれる頼りになるお薬です。効果を実感できるまでには時間がかかることもありますが、医師の指示通りに毎日コツコツと続けることが大切です。
一方で、バルプロ酸は、特に妊娠可能な女性が服用する際には、胎児への影響について細心の注意が必要なお薬です。また、眠気や肝機能障害、体重増加などの副作用にも気をつける必要があります。
一番大切なのは、バルプロ酸について正しい知識を持ち、医師や薬剤師としっかりとコミュニケーションを取りながら、二人三脚で治療を進めていくこと。そして、自己判断で量を調整したり、急にやめたりしないことです。定期的な検査も忘れずに受けましょう。
この記事が、バルプロ酸に対する皆さんの疑問や不安を少しでも軽くして、安心して適切な治療に取り組むためのお手伝いができれば、心から嬉しいです。つらい症状が少しでも和らぎ、より穏やかで快適な毎日が送れるようになりますように。どうぞお大事になさってくださいね。
ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。
(全国からご自宅で受診可能です。)
片頭痛などの頭痛にお悩みの方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。
診療時間:09:00 – 22:00
予約は24時間可能!