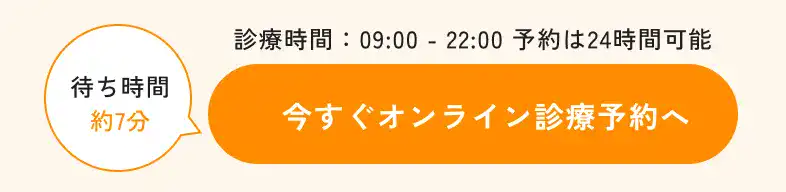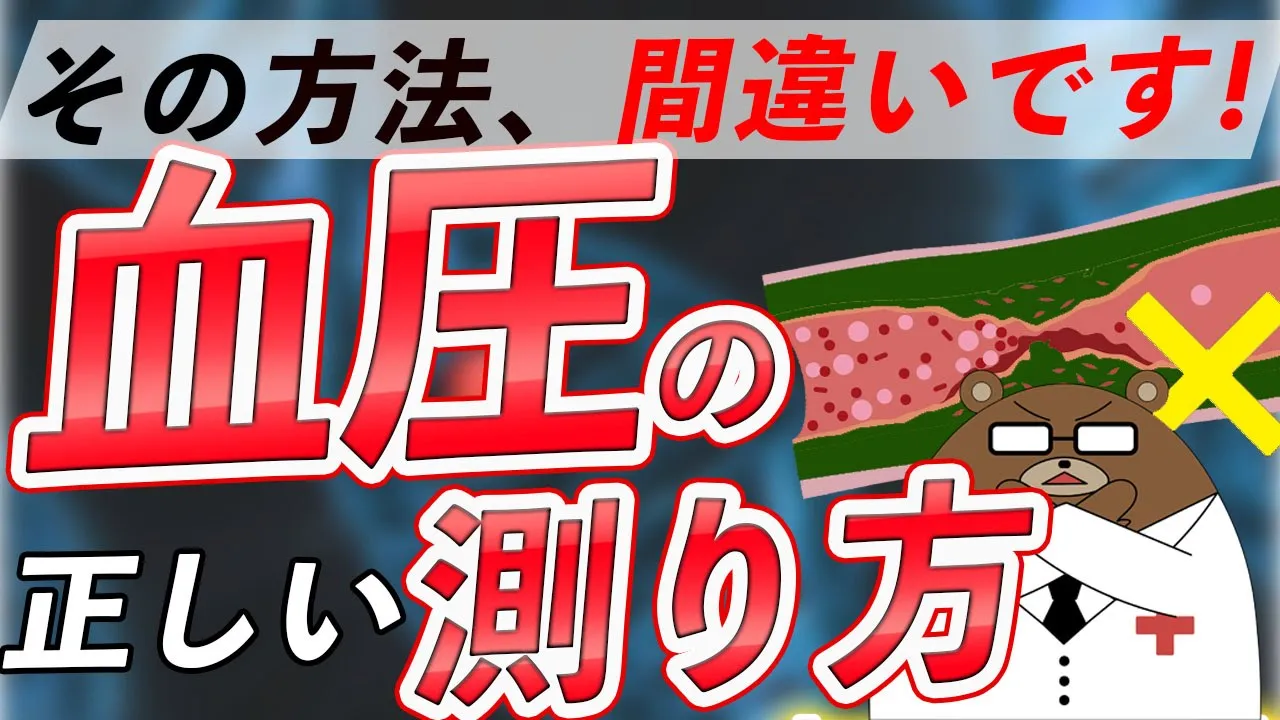「ストレスでイライラするし、食欲もなくて胃がもたれる…」「子どものかんしゃくがひどいけど、胃腸も弱いみたい」
そんな、神経の高ぶりと、胃腸の弱さが同時に見られる不調に、漢方薬の「抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)」が使われることがあります。
この記事では、「抑肝散」の改良版である抑肝散加陳皮半夏について、その効果の仕組みや副作用、そして正しい飲み方を、医師が分かりやすく正確に解説していきます。
漢方の処方は
ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
漢方のオンライン診療
目次
抑肝散加陳皮半夏とは?効果は?
抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)は、神経の高ぶりを鎮める漢方薬「抑肝散」に、胃腸の働きを助ける生薬である「陳皮(チンピ)」と「半夏(ハンゲ)」を加えた、よりマイルドな処方です。 イライラや不眠といった精神神経症状と、食欲不振や胃もたれといった消化器症状が両方ある方に適しています。
医療用では、主に「ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)」のように、製薬会社名がついたエキス剤(粉薬)が処方されます。
抑肝散加陳皮半夏の成分
抑肝散加陳皮半夏は、以下の9種類の生薬(しょうやく)で構成されています。
- 抑肝散の構成生薬(7種類):釣藤鈎、柴胡、当帰、川芎、白朮、茯苓、甘草
→高ぶった神経(漢方でいう「肝」)を鎮め、心身の緊張を和らげる。 - 陳皮(チンピ)
→気の巡りを良くし、胃腸の働きを整える。ミカンの皮。 - 半夏(ハンゲ)
→吐き気を鎮め、胃のつかえ感を取る。
基本的な「神経を鎮める」働きは抑肝散と同じですが、陳皮と半夏が加わることで、胃腸を守り、消化機能を助ける作用がプラスされています。そのため、胃腸が弱い方でも安心して服用しやすくなっています。
抑肝散加陳皮半夏の効果
神経の高ぶりを鎮め、心身の緊張をほぐします。
- イライラ、怒りっぽいなどの神経症状
- 不眠症
- 小児の夜泣き、かんしゃく(疳の虫)
- 胃腸が弱く、食欲不振や胃もたれがある
どんなときに使う?(適応疾患・部位)
- 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症状
- 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(かんしょう)、更年期障害、血の道症、歯ぎしり
抑肝散加陳皮半夏はオンライン診療で出せる?
「イライラが酷い、寝つきの悪さまで出てきた…」「急に症状が出たけど、病院に行く時間がない…」
そんな方に知っていただきたいのが、オンライン診療という選択肢です。
抑肝散加陳皮半夏のような漢方も、医師が適切と判断すれば、オンライン診療で相談したり、処方を受けたりすることが可能です。
ご自宅や職場など、好きな場所からスマートフォンやパソコンを使って医師の診察を受けられ、お薬も自宅に届けてもらえるので、通院の手間や待ち時間をぐっと減らすことができます。
ウチカラクリニックでも、
抑肝散加陳皮半夏に関するご相談や継続的な処方をオンライン診療にて承っております。
特に、症状が安定している場合の継続処方や、お薬への切り替え相談などに、オンライン診療は便利です。経験豊富な医師が親身になってお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。
抑肝散加陳皮半夏の使い方(用法・用量)
1日2〜3回、1回1包(2.5g)を食前または食間(食事と食事の間)の空腹時に服用するのが基本です。年齢や体重、症状により調整されるので、必ず医師の指示通りに使用してください。
通常、そのまま水や白湯で服用しますが、お湯に溶かして、香りや温かさを感じながら飲むと、より効果的とされることもあります。
抑肝散加陳皮半夏の副作用
漢方薬は作用が穏やかですが、副作用が全くないわけではありません。
主な副作用
- 発疹、かゆみなどの皮膚症状
- 胃の不快感、食欲不振、吐き気などの消化器症状
構成生薬の「甘草(カンゾウ)」の長期・大量服用により、偽アルドステロン症がまれに起こることがあります。主な症状は、むくみ、血圧の上昇、手足の脱力感・しびれ、筋肉痛などです。
頻度は極めてまれですが、肝機能障害、間質性肺炎も報告されています。初期症状(だるさ、黄疸、発熱、空咳、息切れなど)に注意が必要です。
副作用が出たときの対処法
何か異常を感じた場合は、服用を中止し、速やかに医師や薬剤師に相談してください。
抑肝散加陳皮半夏の注意事項(禁忌)
使ってはいけない方
- 過去にこの薬の成分でアレルギー症状を起こしたことがある方(禁忌)
- ご高齢の方
- 高血圧、心臓病、腎臓病で“むくみやすい”体質
併用に注意が必要な薬
- 他の漢方薬(特に「甘草」を含むもの)を服用中の方
- ループ利尿薬→低カリウム血症リスク
- ステロイド薬・グリチルリチン含有薬→偽アルドステロン症リスク↑
使用上の注意
漢方薬は、症状だけでなく、その人の体質(「証」といいます)に合わせて選ばれます。
1日3回きちんと続け、2週間経っても変化がなければ医師へ相談しましょう。
保管方法
- 直射日光・高温多湿を避け、室温で保管してください。
- 子どもの手の届かない場所へ。
飲み忘れたら?
気づいた時点で、できるだけ早く1回分を服用してください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分はとばして、次の時間に1回分だけ飲みましょう。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
ウチカラクリニックのオンライン診療でも、抑肝散加陳皮半夏をはじめとした漢方の処方なども行っています。気になる症状がある方はいつでもお気軽にご相談ください。年中無休で診察しています。

抑肝散加陳皮半夏に市販薬はある?値段は?
市販薬
「ツムラ漢方抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒」や「クラシエ薬品「クラシエ」漢方抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒」などの名前で、多くのメーカーから市販されています。
ジェネリック
漢方薬には、西洋薬のような「ジェネリック医薬品」という概念は厳密にはありません。
しかし、ツムラ以外にも、クラシエなど、複数のメーカーが同じ「抑肝散加陳皮半夏」という名称で医療用エキス製剤を製造しており、薬価もそれぞれ異なります。
薬価
時期や規格によって金額は変わってきますが、以下のような目安です。
- ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用):約37.3円/包(3割負担の場合:約11円)
- クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(医療用):約20.3円/包(3割負担の場合:約6円)
※2025年6月4日現在
※薬価は改定などで変わる可能性があります。
添付文書
よくある質問(FAQ)
Q. 妊婦や授乳中でも使えますか?
比較的安全に使えるとされていますが、漢方薬も薬です。自己判断で使用せず、必ず医師に相談してください。特に、妊娠中は体質が変化しやすいため、慎重な判断が必要です。
Q. 子供でも使えますか?
はい、特に胃腸が弱く、食が細いお子様の夜泣きやかんしゃくに使われることがあります。 ただし、お子様の場合は、体重や年齢に応じて服用量を細かく調整する必要がありますので、必ず医師の指示に従ってください。
Q. いつから効きますか?
漢方薬は、体質をじっくりと改善していくお薬です。即効性は期待できません。個人差はありますが、まずは2週間〜1ヶ月程度、毎日きちんと飲み続けることで、イライラや不眠などの症状が少しずつ和らいでくるのを感じられることが多いです。
Q. 睡眠薬とは違うのですか?
全く違います。 睡眠薬が脳に直接作用して強制的に眠気を引き起こすのに対し、この薬は、眠りを妨げている神経の高ぶりや不安を鎮めることで、自然な眠りに入りやすくするお薬です。
Q. 「抑肝散」との一番の違いは何ですか?
胃腸をいたわる生薬(陳皮・半夏)がプラスされている点です。神経の高ぶりを鎮める基本の効果は同じですが、胃腸が弱く、食欲不振や胃もたれを伴う方には、こちらの処方の方がより適しています。
まとめ
抑肝散加陳皮半夏は、神経の高ぶりを鎮める「抑肝散」に、胃腸の働きを助ける効果をプラスした、よりマイルドな漢方薬です。
イライラや不眠と、食欲不振や胃もたれの両方の症状にお悩みの方に適しています。 効果を実感するには、毎日コツコツと飲み続けることが大切です。心と体の両方の不調を感じている方は、一度、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談してみてはいかがでしょうか。
漢方の処方は
ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
漢方のオンライン診療