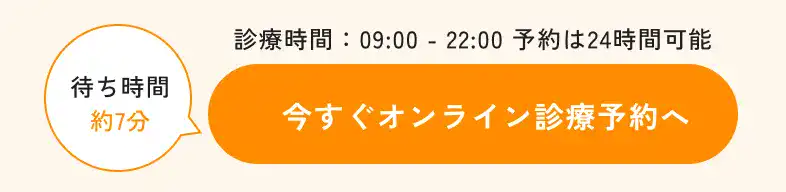「足の指の間が、むずがゆくて皮がむける…」 「もしかして、これって水虫?でも、治らないイメージがあって不安…」
特にジメジメする季節になると気になる足のトラブル。それは、日本人の数人に一人が経験するとも言われるほど、ありふれた皮膚の感染症「水虫(みずむし)」かもしれません。
水虫は決して恥ずかしい病気や治らない病気ではなく、正しい知識でしっかり治療すれば、きちんと治すことができます。水虫の種類と原因から、お薬の解説、うつさないための予防法まで、分かりやすく解説していきます。
もしかして水虫?そんなときは
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
皮膚科のオンライン診療
水虫(白癬)とは?原因は「白癬菌」
水虫の医学的な名称は「足白癬(あしはくせん)」と言います。
その原因は、「白癬菌(はくせんきん)」というカビ(真菌)です。
白癬菌は、皮膚の一番外側にある「角質層」に含まれるケラチンというタンパク質をエサにして増殖します。この菌が、足という靴下や靴で高温多湿になりやすい環境で、爆発的に増えてしまうことで、つらいかゆみや皮むけといった症状を引き起こすのです。
足の水虫、3つの症状
水虫は、症状の現れ方によって主に3つのタイプに分けられます。
趾間型(しかんがた)

水虫の中で最も多く見られる、いわゆる「水虫」のイメージに最も近いタイプです。特に、指と指の間隔が狭く、蒸れやすい薬指と小指の間によく発症します。
症状
- 湿潤型:
梅雨時や夏場に悪化しやすく、指の間が白くふやけて、皮がドロっとむけるのが特徴です。強いかゆみを伴い、皮がむけた部分が赤くただれることもあります。 - 乾燥型:
冬場など乾燥する季節に目立ちやすく、指の間の皮膚がカサカサして、白っぽく細かく皮がむけてきます。
注意点
皮がむけて皮膚のバリア機能が壊れた部分から、細菌が入り込んで炎症を起こし、足全体が腫れあがる二次感染(蜂窩織炎など)を引き起こすことがあるため、早めの治療が大切です。

小水疱型(しょうすいほうがた)

主に土踏まずや足の側面、指の付け根あたりに、米粒くらいの大きさの、少し硬い小さな水ぶくれ(水疱)がポツポツと現れるタイプです。
症状
最初は透明感のある水ぶくれですが、時間が経つと赤みを帯び、やがて乾燥して皮がむけてきます。
新しい水ぶくれと古い皮むけが混在することも多く、非常に強いかゆみを伴うのが特徴です。
注意点
かゆみが強いからといって掻き壊してしまうと、水ぶくれが破れて中の液体(滲出液)が出て、さらに症状が広がってしまうことがあります。また、細菌感染の原因にもなるため、掻かないように注意が必要です。

角質増殖型(かくしつぞうしょくがた)

かかとを中心に、足の裏全体の皮膚が、まるで象の皮膚のように厚く、硬くなるタイプです。
症状
皮膚がゴワゴワになり、表面は乾燥して白い粉をふいたようになります。
冬場など乾燥する季節には、深いひび割れ(あかぎれ)ができて、歩くと痛みを伴うこともあります。
注意点
このタイプの一番の特徴は、かゆみがほとんどない、あるいは全くないことです。ご本人は水虫だと気づかず、単なる「かかとの乾燥」や「加齢によるもの」と長年放置してしまいがちです。皮膚の奥深くまで菌が潜んでいるため、市販の塗り薬だけでは治りにくく、皮膚科での専門的な治療(飲み薬など)が必要になることが多いです。

全身に広がる水虫(白癬)の症状
足の水虫を「かゆくないから」と治療せずに放置していると、原因である白癬菌は、自分の体の他の部位にも感染を広げてしまうことがあります。かゆい足を触った手や、体を拭いたタオルなどを介して、菌が他の皮膚に付着してしまうのです。
爪水虫(爪白癬 :つめはくせん)

足の水虫から最も感染しやすい部位が「爪」です。白癬菌が爪の中に侵入して起こります。
症状
爪が白や黄色に濁る、爪が分厚く変形し、もろくなってポロポロと崩れる、爪の先に白い筋状の模様が入る、などが特徴です。かゆみや痛みはほとんどありません。
注意点
症状がないため放置されがちですが、爪全体が菌の貯蔵庫となり、いくら足の皮膚を治療しても、ここから菌が供給されて足の水虫が再発する原因になります。また、塗り薬が浸透しにくいため、皮膚科での飲み薬による治療が基本となります。
手白癬(てはくせん)

水虫に感染している足を触った手から、感染が広がります。不思議なことに、片方の手だけに症状が出ることが多いのが特徴です(利き手など、よく足を触る方の手)。
症状
足の「角質増殖型」と同じように、手のひら全体の皮膚がカサカサと乾燥し、皮がむけ、皮膚のシワ(掌紋)が深く目立つようになります。かゆみは少ないことが多いです。
体部白癬(たいぶはくせん) 【ぜにたむし】

腕、脚、お腹、背中など、体の柔らかい部分に感染したものです。
症状
輪郭がはっきりした、円形〜楕円形の赤い発疹ができます。輪の部分が少し盛り上がって、かゆみが強く、中心部は治ったように見えるのが典型的な見た目です。
股部白癬(こぶはくせん)【いんきんたむし】

足や爪の白癬菌が、タオルや手などを介して、股間(内もも、お尻など)に感染した状態です。高温多湿で蒸れやすいため、菌が増殖しやすい部位です。
症状
体部白癬と同様に、半円状のくっきりとした赤い発疹ができ、非常に強いかゆみを伴います。
頭部白癬(とうぶはくせん)【しらくも】

白癬菌が頭皮の毛穴に感染したものです。お子さん(特に格闘技など、頭を接触させる機会のある場合)に多いですが、大人でも感染します。
症状
フケが大量に出たり、円形に髪の毛が抜けたり、切れやすくなったりします。フケ症や円形脱毛症と間違われることもあり、正確な診断が重要です。
このように、白癬菌は全身のどこにでも感染する可能性があります。
足の水虫をしっかりと治しきることが、全身への感染拡大を防ぐための最も重要な第一歩なのです。
水虫はうつる?主な感染経路
水虫は他の人にうつります
水虫(足白癬)は、原因である白癬菌が他の人に移ることで広がる「感染症」です。特に、カーペットや足ふきマットなどを共有する同居のご家族がいる場合は、感染を広げてしまうリスクがあります。
ただし、菌が足に付着した瞬間に、すぐに感染が成立するわけではありません。感染の仕組みを正しく知ることが、予防への第一歩となります。
主な感染源
水虫の原因となる白癬菌は、感染した人の足から剥がれ落ちた皮膚の垢(あか)の中に潜んでいます非常に生命力が強く、剥がれ落ちた垢の中でも数ヶ月以上生き続けることができます。
この菌は、高温多湿な環境を好み、特に以下のような場所が主な感染源となります。
- 家庭内 ご家族が共用する足ふきマット、バスマット、スリッパ、そして菌を含んだ垢が落ちやすい畳やフローリング、カーペットなど。
- 公共施設 スポーツジム、温泉、銭湯、サウナ、プールの更衣室やシャワー室の床・足ふきマット。不特定多数の人が裸足で利用する場所は、特に注意が必要です。

感染の仕組み
菌が足に付着した瞬間に100%うつるわけではありません。感染が成立するには、いくつかの条件がそろう必要があります。
- 菌の付着 感染源となっている場所を素足で歩くことで、白癬菌を含んだ皮膚の垢が足に付着します。
- 菌の潜伏 付着した菌は、すぐに洗い流せば感染には至りません。しかし、そのまま放置されると、皮膚の表面にとどまり続けます。
- 菌の侵入・増殖 足が靴や靴下の中で蒸れて、高温多湿な状態が24時間以上続くと、菌が皮膚の最も外側にある角質層に侵入し、増殖を始めます。この時点で、「水虫に感染した」ということになります。
逆を言えば、たとえ菌が付着しても、24時間以内に足を石鹸で丁寧に洗い、清潔で乾燥した状態を保てば、感染のリスクは大幅に減らせるということです。
水虫は何科?受診の目安は?
「このくらいで病院に行くのは大げさかな?」と迷うかもしれません。
市販薬で対応するか、病院へ行くべきか迷ったときは、以下の項目をチェックしてみてください。
水虫のチェックリスト
□ 市販薬を2週間〜1ヶ月使っても、症状が全く改善しない
□ かゆみや痛みが非常に強い、または水ぶくれがひどい
□ じゅくじゅくして化膿している、またはひどい臭いがする
□ かかと全体がガサガサで、ひび割れている(角質増殖型の疑い)
□ 爪が白や黄色に濁ったり、分厚く変形したりしている(爪水虫の疑い)
□ 本当に水虫か自信がない(他の病気の可能性)
□ 足以外にも、手や体にも似たような症状が広がってきた
上記のチェックリストに一つでも当てはまる場合や、早く確実に治したい場合は、「皮膚科」を受診しましょう。皮膚科では、皮膚の専門家が症状を正確に診断してくれます。
特に、顕微鏡検査で皮膚の角質を少し採取し、白癬菌がいるかどうかをその場で確認してくれるため、「本当に水虫なのか」を確実に知ることができます。
これにより、水虫ではない他の皮膚病(汗疱や接触皮膚炎など)との見間違いを防ぎ、最適な治療を始めることができます。

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!
「治療を始めてみたいけど受診がめんどう」「仕事が忙しくて、平日に病院に行く時間がない」
そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。
オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。
保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!
\ オンライン診療の3つのメリット /
①自宅で完結、待ち時間ゼロ
予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。
24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!
診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。
薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。
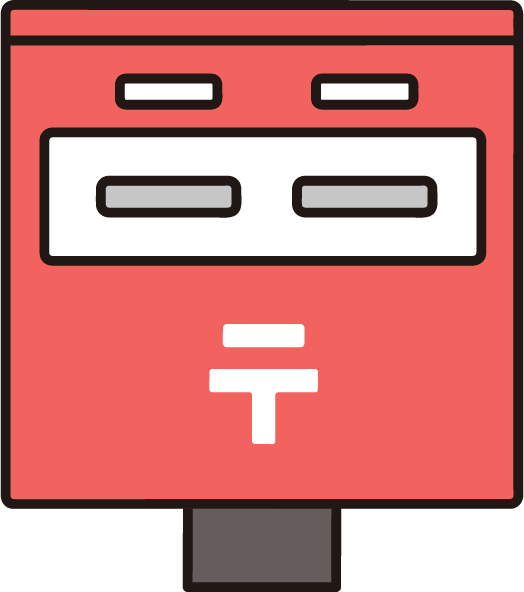
③感染リスクなし
病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。

水虫の処方薬はなにがある?主な抗真菌薬の特徴
水虫治療の基本は、原因である白癬菌を殺す、または増殖を抑える「抗真菌薬」の塗り薬を、根気よく続けることです。
\ 市販薬についての解説は /
\ こちらの記事をチェック! /
ラミシールクリーム(テルビナフィン)

| 有効成分 | テルビナフィン塩酸塩(アリルアミン系) |
| 働き(作用機序) | 真菌(カビ)の細胞膜をつくるのに必要な「エルゴステロール」という成分の合成を初期段階でブロックします。これにより、白癬菌を死滅させる強力な殺菌作用を発揮します。 |
| ポイント | 市販薬としても有名ですが、医療現場でも水虫治療の第一選択薬として長く使われています。その高い殺菌力で、原因菌をしっかりと退治する、信頼性の高い薬です。 |
ゼフナートクリーム

| 有効成分 | リラナフタート(チオカルバミン酸系) |
| 働き(作用機序) | ラミシールと同様に、エルゴステロールの生合成を阻害することで殺菌的に作用します。 |
| ポイント | 皮膚の角質層への浸透性が高く、長く留まる性質があります。そのため、1日1回の使用で効果が持続しやすく、塗り忘れが心配な方や、日中塗り直しが難しい方にも適しています。 |
ケトコナゾールクリーム(ニゾラールなど)

| 有効成分 | ケトコナゾール(イミダゾール系) |
| 働き(作用機序) | こちらもエルゴステロールの生合成を阻害しますが、主に菌の増殖を抑える静菌作用によって効果を発揮します。 |
| ポイント | 水虫(白癬菌)だけでなく、皮膚カンジダ症や癜風(でんぷう)、脂漏性皮膚炎の原因とされるマラセチア菌など、より幅広い種類の真菌に効果を示すのが最大の特徴です。 |
正しい水虫の薬の塗り方
お風呂上がりの清潔な肌に塗るのが最も効果的です。
指の間から足の裏全体、かかと、アキレス腱のあたりまで、症状がない部分にも広範囲に塗ることが再発防止のコツです。
見た目がきれいになっても、角質層の奥に菌が潜んでいます。症状が消えても、最低1ヶ月は塗り続けましょう。根気強く続けることが完治への一番の近道です。

水虫を再発させない!うつさない!予防とセルフケア
足を清潔に保つ

白癬菌の温床となる古い角質や、栄養源となる皮脂・汚れをしっかり洗い流すことが基本です。
石鹸をよく泡立て、ゴシゴシせず、足の指の間や爪の周りまで丁寧に洗いましょう。皮膚を傷つけると、菌が侵入しやすくなるため、洗いすぎも注意です。
しっかりと乾燥させる

白癬菌は高温多湿の環境を好みます。入浴後はもちろん、日中汗をかいた後も、清潔なタオルで水分を拭き取りましょう。
特に水分が残りやすい足の指の間は、タオルを指に挟むようにして一本ずつ丁寧に拭き取ってください。
通気性を良くする

一日中履いた靴の中は、汗によって高温多湿になり、白癬菌にとって絶好の繁殖場所となります。
同じ靴を毎日履くのは避け、最低でも2〜3足をローテーションさせて、履かない靴は風通しの良い場所でしっかり乾燥させましょう。また、通気性の悪い革靴やブーツを長時間履くのはなるべく避け、吸湿性の良い綿素材や、指の間のムレを防ぐ5本指ソックスを選ぶのもオススメです。
家族への感染を防ぐ
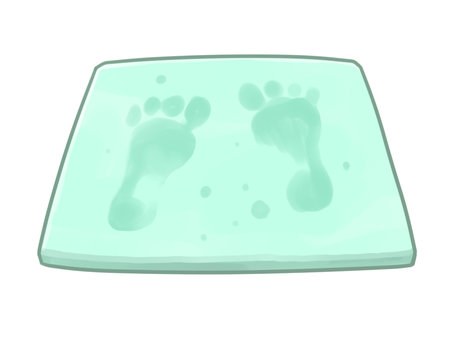
水虫は、感染者が歩いた床に落ちた角質(垢)に触れることで感染します。家庭内感染を防ぐため、バスマットや足ふきタオル、スリッパなどは個人専用にしましょう。
また、白癬菌は角質の中で生き続けます、リビングや脱衣所などの床はこまめに掃除機をかけ、菌が潜むエサをなくしましょう。
まとめ
水虫(足白癬)は、「白癬菌」というカビが原因の、治療可能な感染症です。
治療の鍵は、①症状に合った薬を、②正しく(広く・長く)塗り続けること。そして、完治後も足を清潔・乾燥に保つという日々のケアを続けることが、再発と家族への感染を防ぐために何より重要です。
「本当に水虫かな?」「市販薬で良くならない」と悩んだら、自己判断を続けずに、ぜひ一度お近くの皮膚科で相談してみてください。
もしかして水虫?そんなときは
ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療
- 全国から自宅で受診可能
- 診療時間:07:00-22:00
 オンラインで
オンラインで診察相談する 24時間
受付
※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。
皮膚科のオンライン診療
この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師
森 勇磨
経歴
東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)
YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。